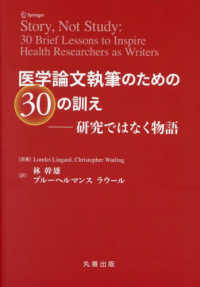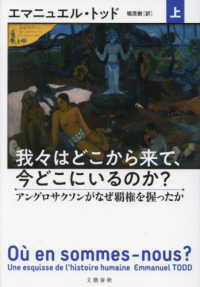内容説明
故郷沖縄での苦しい生活を脱するため20世紀前半に多くの人々がアルゼンチンへ雄飛したが、そこでの暮らしは必ずしも思い描いていた通りのものではなかった。貧困や差別のある厳しい生活の中で培われたアイデンティティや連帯の強さは、しかし、「沖縄」「同郷」というだけで説明できるような、わかりやすいものなのだろうか。戦後に在亜沖縄県人連合会が結成された経緯と意義を、そして戦争や帰属問題に揺れる遠くの故郷をどのように移民の人々が見ていたのかを、「エスニシティ」や「ナショナリズム」に還元できないものに目を向けながら描きだす。
目次
第1章 アルゼンチンにおける沖縄移民社会の形成
第2章 沖縄移民の団体・仕事・生活
第3章 第二次世界大戦時の在亜邦人社会と沖縄移民
第4章 在亜邦人社会の戦後―アルゼンチン政府要人への接近と移民の再開
第5章 救済活動による戦後組織の展開
第6章 沖縄文化の抑圧とアルゼンチンにおける沖縄文化
第7章 「在亜沖縄県人連合会」の設立
著者等紹介
月野楓子[ツキノフウコ]
沖縄国際大学総合文化学部専任講師。沖縄移民研究、国際文化学、ラテンアメリカ研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 食品の栄養とカロリー事典 第3版 1個…