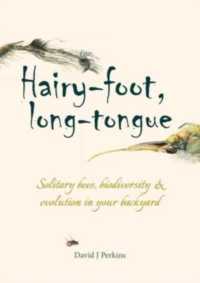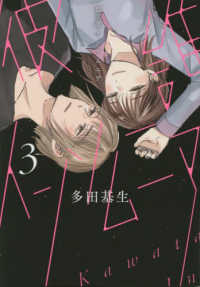内容説明
私たちの行為や現実は、学習とどのように結びつきうるか?1970年代以降のドイツの学校教育改革の変遷を、様々な授業実践の具体例をもとに考究。教育の営為における学習/教授や改革/反改革の両義的な発想を捉え、学ぶことと生きることの連関を描きつつ、多視点性を活かす差異に基づく授業の構想と方法を提言する。
目次
なぜ、学校と生活の接続が問題となるのか
第1部 1970年代の急進的な学校批判とオルタナティブ学校の創設(西ドイツにおける学校批判とグロックゼー学校―「68年運動」に根差す学校と生活の接続方法;批判と修正の中のグロックゼー学校―顕在化するヘンティッヒ・パラドックスとの対峙)
第2部 1980年代以降の改革教育的な授業改革と改革批判(学校と生活を接続する「実践的学習」の構想と実践―学習における実践的な行為の要求とそれに対する教授学的批判;教育政策に浸透する「学校の開放」の要求―ノルトライン・ヴェストファーレン州の基本構想「学校生活の形成と学校の開放」をめぐって;プランゲの学校論における「反省的学習」―生活との差異に基づく授業の構成理論)
第3部 1990年代以降の改革教育批判の改革教育(改革教育の批判的継承としての学校実験「イエナ‐プラン・ヴァイマール」―多視点的授業と対話的教育に基づく授業改革;「ヨーロッパ・プロジェクト」における多視点的授業のモデル化と実践―現実を観察する「多」視点的な授業構成モデルの構築とその特徴)
本書の結論と展望
著者等紹介
田中怜[タナカレイ]
育英大学教育学部講師。筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程学校教育学専攻修了。博士(教育学)。筑波大学大学院教育研究科特任研究員を経て現職。専門は教育方法学。主な論文に、「プランゲの学校論における反省的学習(reflexives Lernen)―生活との差異に基づく学校教授構想の展開」『教育方法学研究』第42巻、日本教育方法学会、2017年(日本教育方法学会研究奨励賞受賞論文)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 黒鷺死体宅配便(26) 角川コミックス…