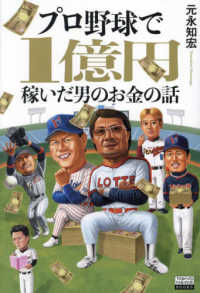出版社内容情報
ヒンドゥー教が圧倒的に優勢なインドで、なぜイスラーム建築が今も多数残っているのか。一次史料をもとに物語風に叙述しながら、インドの歴史遺産をめぐる知的ガイドブック。 写真多数掲載。
第1章 トルコ系民族のインド侵入
第2章 デリー・スルターン朝(1206?1320年)
第3章 デリー・スルターン朝(1320?1413年)
第4章 デリー・スルターン朝(1414?1526年)
第5章 ムガル帝国(1526?56年)
第6章 ムガル帝国(1556?1627年)
第7章 ムガル帝国(1628?1707年)
宮原辰夫[ミヤハラタツオ]
文教大学国際学部国際観光学科教授。著書に『イギリス支配とインド・ムスリム』(成文堂1998)など。
内容説明
クトゥブ・ミーナール、フマーユーン廟、タージ・マハル―世界遺産の間に埋もれた歴史遺産を巡る旅。希代の大旅行家イブン・バットゥータやベルニエたちが誘う、インド・イスラームの世界。知的好奇心を刺激する待望のガイドブック。カラー写真多数満載。
目次
第1章 トルコ系民族のインド侵入
第2章 デリー・スルターン朝(一二〇六~一三二〇年)―クトゥブ・ミーナール
第3章 デリー・スルターン朝(一三二〇~一四一三年)
第4章 デリー・スルターン朝(一四一四~一五二六年)
第5章 ムガル帝国(一五二六~五六年)―フマーユーン廟
第6章 ムガル帝国(一五五六~一六二七年)―アーグラー城塞
第7章 ムガル帝国(一六二八~一七〇七年)―タージ・マハル、ラール・キラー
著者等紹介
宮原辰夫[ミヤハラタツオ]
慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。博士(法学)。現在、文教大学国際学部教授。専攻、政治学、地域研究(南アジア)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
naoto
ちなつ
-
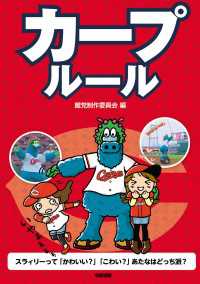
- 電子書籍
- カープルール 中経出版