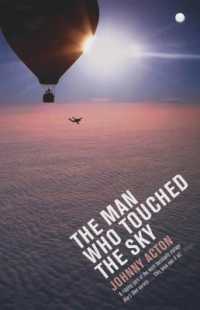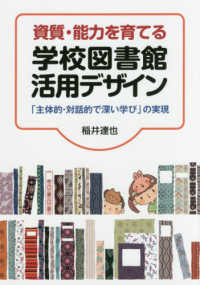内容説明
激動する時代状況に身を置きつつ、つねに世界的な課題を視野に入れ、日本語の表現を切り拓いていった文豪たちの歩みを、テクストに即したどる。“近代”とは何かを問い続けた思想家として鴎外・漱石を読むスリリングな試み。
目次
鴎外とラディカリズムの精神―醇化する言語芸術的意識
越境するラディカリズム―初期鴎外における“ジャンル”の抗争
『隠微』を拓く言葉たち・“近代小説”史の古層―「舞姫」の“問い”1
“捉え難き内部”、または、曇れる『胸中の鏡』―「舞姫」の“問い”2
不可知なる自己―“世紀転換期”と“鴎外”的問題構制の始発
“創作家への転生”、あるいは、自己解体―再稼動する鴎外の精神
果たされなかった『技癢』の行方―「木精」の『寓意』のことなど
『自由』と『伝承』と―鴎外・漱石の“近接”問題
『情熱の否定』と『非人情』―一九〇六、鴎外・漱石と先端性
ジャンルの交錯・ドラマと小説と―鴎外「半日」の芸術史的位置〔ほか〕
著者等紹介
大石直記[オオイシナオキ]
1957年生。共立女子大学文芸学部教授。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程中途退学。四国大学講師・埼玉大学助教授を経て、現職。日本近代文学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
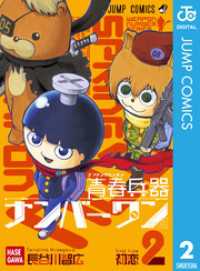
- 電子書籍
- 青春兵器ナンバーワン 2 ジャンプコミ…
-

- 電子書籍
- 当選 Vol.4