- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
目次
第1章 コミュニケーションとは何か?
第2章 コミュニケーションというコインのもう一つの面:理解
第3章 話せないのか?コミュニケートできないのか?
第4章 なぜ子どもはそうしたのか?行動とコミュニケーションの関係
第5章 拡大・代替コミュニケーション・システム(パット・ミレンダとブレンダ・フォセット)
第6章 絵カード交換式コミュニケーション・システム(PECS):最初のトレーニング
第7章 PECSの上級レッスン
第8章 理解の視覚的支援
著者等紹介
園山繁樹[ソノヤマシゲキ]
島根県立大学人間文化学部/教授、筑波大学/名誉教授。博士(教育学)/自閉症スペクトラム支援士(EXPERT)、臨床心理士、臨床発達心理士
竹内康二[タケウチコウジ]
明星大学心理学部/教授。博士(心身障害科学)/公認心理師、臨床心理士
門眞一郎[カドシンイチロウ]
フリーランス児童精神科医、ピラミッド教育コンサルタント社(米国)/名誉コンサルタント(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
むつ
6
7歳までに話せるようになっていなければ、話せるようになる可能性は低く、代替手段を用いた機能的コミュニケーション・スキルの獲得に焦点を合わせるのが適切。問題行動をなくそうとするのではなく、問題行動の理由を調べ、その問題行動を私たちが受け入れやすく、子ども自身の目的に適う行動に変えるのがよい。「言葉を話せない子どもにコミュニケーションの支援をすることは、おそらくあなたが贈ることのでできる最高に価値ある贈り物なのです。」PECSの最初の目的は、他の人とのやりとりを自分から始めることを子どもに教えること。2022/07/28
Totsuka Yoshihide
2
実践の振り返りのために読みむした。2022/07/17
縁
0
コミュニケーションを育てること。強制から自発への移行可能性。順を追ってひとつずつ。子どもを知ることが必要。大切なのはその背景にある考え方。2025/02/11
-
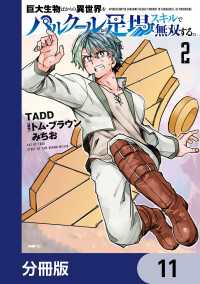
- 電子書籍
- 巨大生物ばかりの異世界をパルクールと足…







