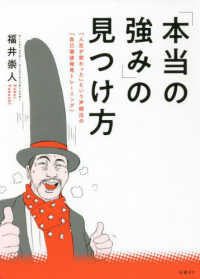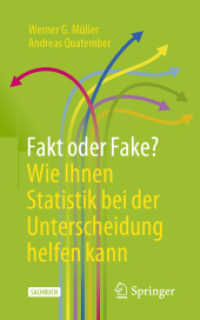内容説明
ロジカルにカオスと戯れる。それがジェネラティブ・アート。アーティストのためのプログラミング言語「Processing」を使って、美しく予測不可能な「ジェネラティブ・アート」をスケッチしよう!
目次
1 クリエイティブ・コーディング(ジェネラティブ・アート:理論と実践;Processing:アーティストのためのプログラミング言語)
2 ランダム性とノイズ(線を引く間違った方法;円を描く間違った方法;次元を加える)
3 複雑性(創発;自律性;フラクタル)
著者等紹介
久保田晃弘[クボタアキヒロ]
1960年生まれ。1988年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了・工学博士。多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース教授
沖啓介[オキケイスケ]
アーティストとして多摩美術大学の学生のころから現代美術の作品を国内外で発表しはじめ、またビデオアート、パフォーマンス、電子音楽などのメディアアートに深く関わる。カーネギーメロン大学STUDIO for Creative Inquiry研究員を経て、東京造形大学特任教授、名古屋造形大学客員教授のほか、早稲田大学理工学術院基幹理工学部表現工学科、武蔵野美術大学デザイン情報学科などで教えている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kumokumot
6
コードに偶発性を持ち込むことで、想像もしない美しさが現れる魅力。原理の先にアートがあることそのものが美しいと思う。2020/07/16
汐除明
4
Processing.orgのチュートリアルを半分くらい終わらせたところで入手。Generative artの根幹であるランダム性についてとても丁寧に解説がなされており、ヒトのそれだった視野が草食動物くらいまで広がった気がする2019/06/02
Mariyudu
4
拗らせるというのは怖いもので、自分が野末のいちブログラマでしか無いしそれで良いと受け入れた今でも時々、「もしかしてアーティストになれるんじゃね?」的な煩悩が目を覚ましたりする。そんな流れか最近、パーリンノイズを使ったとある作画処理を試みてたんだけど行き詰まって、本書を手にとってみた。それほど詳しい情報は無かった反面、頼みもしないアーティスト指南がてんこ盛りで、そういう本だったのかと苦笑しながら読了。2017/11/23
Tenouji
3
noise関数がrandom関数と違って、いいね。2020/11/05
かるごん
2
プログラミングの方法論でもなく、アートの解説本でもない、「思考の方法」のようなものを示したいい本。原著読みたいかも。こういう感じの書き方してくれる本が出てくれたらたのしいなー(知ってる方教えてください!)2018/10/21