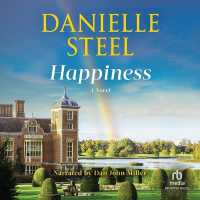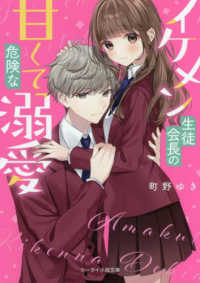内容説明
テクノロジーの進歩によりますます変容する世界を捉え、デザインしていくためには?これからのものづくりのための最重要キーワード「自己帰属感」を軸に、情報を中心とした設計の発想手法を解き明かす。UX、IoTの本質を掴みたい人へ。
目次
第1章 Macintoshは心理学者が設計している
第2章 インターフェイスとは何か
第3章 情報の身体化―透明性から自己帰属感へ
第4章 情報の道具化―インターネット前提の道具のあり方
第5章 情報の環境化―インタラクションデザインの基礎
第6章 デザインの現象学
第7章 メディア設計からインターフェイスへ
著者等紹介
渡邊恵太[ワタナベケイタ]
1981年東京生まれ。博士(政策・メディア)。インタラクションの研究者。知覚や身体性を活かしたインターフェイスデザインやネットを前提としたインタラクション手法の研究に従事。2009年慶應義塾大学政策メディア研究科博士課程修了。2010年よりJST ERATO五十嵐デザインインタフェースプロジェクト研究員。東京藝術大学非常勤講師兼任を経て2013年4月より明治大学総合数理学部先端メディアサイエンス学科専任講師。シールドインタラクションデザイン株式会社代表取締役社長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
izw
12
「デザイン」「インターフェイス」についての認識が新たになりました。ユーザーインタラクションという言葉は知っていましたが、単にモノやその使い方をデザインするのでなく、使う体験をデザインするのだということがやっと実感できた気がします。道具が身体の一部になり、意識せずに使いこなせるようになることを透明性というそうですが、投げたボールはどこまで身体かとか、カーソルは身体の延長か、という考察には考えさせられました。若い著者の気負いからか全体的に読みにくさがありますが、それを補って余りある内容かと思います。2015/11/30
さっとん
10
コンピュータやそれを媒介にしたインターネットが人々の体験をどう変えて行くのかに対する考え方がわかりやすく説明されている。今のコンピュータはタイプライターとテレビが一体になったものにすぎない、という指摘はとても新鮮で、これから様々なインターフェースのインターネット的な体験を生み出すデバイスが続々と現れるだろう。特に、センサー技術と統計的解析の技術の向上はこうした未来に置いてとても重要な分野であることは火を見るより明らかである。2019/03/19
yzyk
9
今まできにせず使っていたiPhoneを自己帰属感や道具の透明性といった視点で見直すと、すごいなーよくできてるなーと感心してしまった。おもしろかった。2019/01/28
kumokumot
6
読んだあと、自分はそれまでUI・UXの言葉をだいぶ浅い意味で使っていたのだと感じた。身体感覚の拡張と、その拡張した身体で得られる新たな知覚。特にユーザーに一番近いところにいる、モバイルアプリ開発者は誰しも読むと学ぶところがある内容に思う。2020/10/18
りんだ
5
数年前に「Appleは好きな人が多いが、Google好きな人は少ない」という話を聞いたことがあった。その話に近く、「自己帰属感」ならびに「生活への溶け込み」が重要であると説いている。 自分に情報を帰属させるには、情報を実世界へ干渉させるインターフェースである必要がある。この情報が人を動かし、事象をコントロールする、ということだ。 そのためには、「自己帰属感」を産むためのインターフェースデザインとともに、人々の生活に情報を溶け込ませる「インタラクションデザイン」が重要なのだろう。 めっちゃ面白い。2023/05/07
-
- 洋書
- Happiness