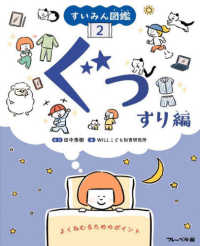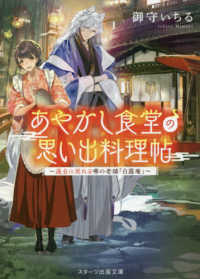内容説明
「人間である」とは?根底から問い返す論攷を核に、「人間であること」の諸相の探求とその教育学的展開からなる人間学の書。
目次
第1部 人間であること―その根底と諸相(人間であること;苦悩の人間学的考察―フランクルの「ホモ・パティエンス」を手がかりにして;ナイチンゲールの積極的神秘主義と看護論における「三重の関心」―ケアの人間学の原点のために;読むことについて―人間学的な一つの省察 ほか)
第2部 人間であること―その教育学的展開(教育のなかの教育―臨床教育学の試み;価値多様化時代における理性の責任―教育課題としての「対話の能力」;浄土の教育学―教育の構造と「私」の本質;西田幾多郎と教育学―「教育学について」を読む ほか)
著者等紹介
上田閑照[ウエダシズテル]
1926(大正15)年1月東京に生まれる。1949(昭和24)年京都大学文学部哲学科を卒業(宗教学専攻)。1959年10月から1962年7月までドイツ、マールブルク大学に留学。1963年2月同大学より「マイスター・エックハルト研究」により哲学博士号を受ける。1976年5月京都大学より「東西神秘主義研究」により文学博士号を受ける。高野山大学(宗教哲学担当)、京都大学教養部(ドイツ語)勤務を経て、1967年4月京都大学教育学部助教授(教育人間学)、1972年4月同学部教授(教育人間学講座担任)、1977年4月京都大学文学部教授(宗教学講座担任)、1989(平成元)年3月末停年退職、京都大学名誉教授となる。2003年12月より日本学士院会員。学会・学界においては、日本宗教学会会長、日本学術会議会員、東西宗教交流学会会長などを歴任、現在コルモス(現代における宗教の役割研究会)会長。西田哲学会会長。研究領域は、宗教哲学、人間存在論、中世ドイツ神秘主義、ドイツ近世・現代哲学、禅仏教、西田哲学及び近代・現代日本の哲学。ドイツ語圏での諸大学における度重なる客員講義の経験から、東西の思想、宗教の出会いを場所とした世界的に通底する人間存在論、宗教哲学の展開を生涯の課題としている
皇紀夫[スメラギノリオ]
大谷大学文学部教授
山田邦男[ヤマダクニオ]
大阪府立大学名誉教授
松田高志[マツダタカシ]
神戸女学院大学文学部教授
吉村文男[ヨシムラフミオ]
奈良産業大学情報学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
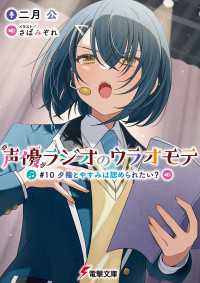
- 電子書籍
- 声優ラジオのウラオモテ #10 夕陽と…
-

- 電子書籍
- Paying it forword