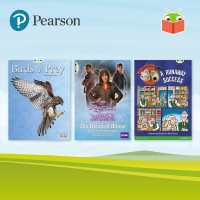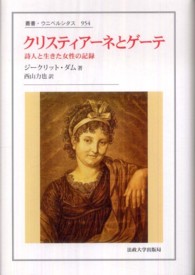内容説明
「ブランコ」はなぜ春の季語なのか?アジサイの学名は長崎の遊女の名前!「雷」と「稲妻」、季が異なるのはなぜ?酉の市にはなぜ熊手を売るのか?俳句がもっと面白くなる歳時記の雑学集。
目次
第1章 春の謎(芭蕉の名句「古池や―」の蛙は何匹かという疑問;「彼岸」はなぜこういう字なのか ほか)
第2章 夏の謎(滝はかつて真っ直ぐに落ちない流れを指した;「雲の峰」とはどんな姿のことか ほか)
第3章 秋の謎(花は変わっても姿に名を託された朝顔;変化朝顔の研究が生んだ科学 ほか)
第4章 冬の謎(日本人の雪に対する観察の細やかさはどこからくるのか;「時雨」はなぜ、詩歌の世界で人気があったのか ほか)
第5章 新年の謎(除夜詣と初詣は同じか;異形の鬼「なまはげ」は働き者の象徴 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
菜花@ほのおかくとう協会門下生
9
大学の図書館にて。単純に日本の季節についての本かと思っていたら、なんと俳句の本でした。それでも、ぼんやりと知っていた有名な歌の具体的な背景を知れたり、昔の風習を知れたりと収穫はありました。特に、晴れた日に雪がちらつく様子を表す「風花」という言葉は、とても気に入りました。しかし、情報量が多すぎるので、俳句素人の私は、一回読んだだけだとほとんど忘れてしまいそうです。2012/11/05
yukioninaite
0
芭蕉はバナナで子規がホトドギスは知っている人は知っていますね。4世紀以前はキリストの誕生日は1月6日とされていたのは知っていましたか?2015/04/19