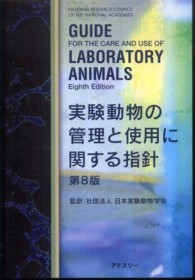内容説明
あらかじめそこで行われることがわかっている建築(遊園地)から、そこで行われることでその中身がつくられていく建築(原っぱ)へ。潟博物館、ルイ・ヴィトン表参道、青森県立美術館、並びにH、Sなど一連の住宅で、今最も注目されている著者の初めての建築論集。
目次
1 そこで行われることでその中身がつくられていく建築(「原っぱ」と「遊園地」;続・「原っぱ」と「遊園地」 ほか)
2 別々のことをしている人たちが時間と空間を共有する(道から進化する建築;決定ルール、あるいはそのオーバードライブ ほか)
3 生活を不定形で連続なものとしてそのままにとらえる(動線体としての生活;窓としての住宅 動線体の開きかた ほか)
4 既存建物もそういう地形とか敷地のかたちと同じである(建築のアクチュアリティ;近代建築とグリッド ほか)
著者等紹介
青木淳[アオキジュン]
1956年神奈川県生まれ。80年東京大学工学部建築学科卒業。82年同大学院修士課程修了。83~90年磯崎新アトリエに勤務。91年青木淳建築計画事務所設立
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Koki Miyachi
3
2004年の本だから少し古い。今や押しも押される建築家として評価される青木淳氏の建築論というか、自分の建築観を率直に語っている書。建築家が、頭の中の思考や発想の原点をストレートに語っている点において稀有な一冊ではないだろうか。その思考は実に独創的で刺激的だ。青木氏の磯崎アトリエ在籍時に、アルバイトとしてお世話になったことがあるが、実に素晴らしい人格者でもある。2021/04/10
ひばりん
3
個人的座右の書。遊園地のように利用者の行動を計画しつくした建築よりも、原っぱのように「ここで何をしよう」と思ってもらえる建築を設計したいという建築家の意思表明の書。そうした姿勢は、とりわけ筆者の美術館建築において貫徹されているが、社会設計・制度設計からデザインにいたるまで、あらゆるジャンルに適応できる考え方であろう。
takao
2
ふむ2022/05/29
チャーリー
2
本の題名にもなっている「原っぱと遊園地」という文章を最初に読んだのは高校生の時だったと思う。模試の題材に使われていたのだ。「原っぱ」というそれ自体は何の明確な機能も想定してない空間と、「遊園地」というある目的のために目的合理的につくられた空間。この本では青木が建築という「つくる」ことによって「原っぱ」をいかにつくっていくか、その建築的格闘が青木自身の言葉で繰り返し述べられている。「空間が先回りして住む人の行為や感覚を拘束する」ことを青木は徹底的に避けようとする。そしてコンテキストにうまく適応する建築を生み2016/10/08
doji
1
場所の用途が用意されている遊園地と、余白のある原っぱというたとえから、どんどんひとと場所のインタラクションの質や、そこで生まれる意味について考え続けていく。物理的に巨大なものというだけでなく、場所性や意味性、そきてそこの歴史的文脈や景観における関係性など、あらゆることがらによって変質していく建築の意味について考察する著者の視点が、とても丁寧で鋭い。震災についての章で、そういった考え方になった理由が納得できた。2020/02/19
-

- 電子書籍
- 青春ロマンス【タテヨミ】第11話 pi…
-

- 電子書籍
- 出世はヨイショが9割