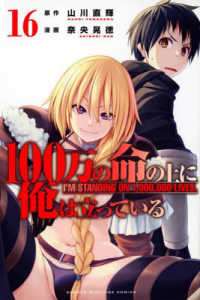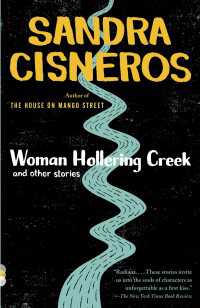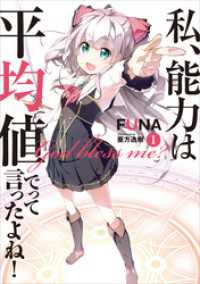内容説明
新型コロナウイルスのパンデミックを経験した人類は、この先どこへ向かうのでしょうか。我々が出した答えが「自在化身体」です。デジタル化の進展で仕事や生活が劇的に変わることは間違いありません。いわゆるデジタルトランスフォーメーション(DX)の潮流です。しかし、そこには人の身体を顧みる視点が欠けています。肉体を置き去りにしたDXは、人々を必ずしも幸福にしないでしょう。自在化身体は、この隔たりに橋を渡します。生理から心理に至る人の成り立ちを深く掘り下げ、リアルな物理世界とバーチャルな情報空間が共存する時代の新しい身体像を提示します。人間は肉体の制約から自由になり、限りなく拡張された能力を自在に使いこなす存在になるはずです。本書は自在化身体の概念と技術を原点から紐解きます。人類の進化はここから始まります。
目次
第1章 変身・分身・合体まで 自在化身体が作る人類の未来
第2章 身体の束縛から人を解放したい コミュニケーションの変革も
第3章 拡張身体の内部表現を通して脳に潜む謎を暴きたい
第4章 自在化身体は第4世代ロボット 神経科学で境界を超える
第5章 今役立つロボットで自在化を促す 飛び込んでみないと自分はわからない
第6章 バーチャル環境を活用した身体自在化とその限界を探る
第7章 柔軟な人間と機械との融合
第8章 情報的身体変工としての自在化技術 美的価値と社会的倫理観の醸成に向けて
著者等紹介
稲見昌彦[イナミマサヒコ]
東京大学総長補佐・先端科学技術研究センター身体情報学分野教授、博士(工学)。日本学術会議連携会員。一般社団法人超人スポーツ協会代表理事。JST ERATO稲見自在化身体プロジェクト研究総括
北崎充晃[キタザキミチテル]
豊橋技術科学大学情報・知能工学系長教授、博士(学術)。日本バーチャルリアリティ学会拡張認知調査研究委員会委員長。日本心理学会代議員、日本基礎心理学会理事、日本バーチャルリアリティ学会評議員。JST ERATO稲見自在化身体プロジェクト認知心理・行動理解グループグループリーダー
宮脇陽一[ミヤワキヨウイチ]
電気通信大学大学院情報理工学研究科機械知能システム学専攻教授、博士(工学)。電気通信大学脳・医工学研究センター。JSTさきがけ研究者。JST ERATO稲見自在化身体プロジェクト研究員。Section on Functional Imaging Methods,Laboratory of Brain and Cognition,National Institute of Mental Health,National Institutes of Health
ガネッシュ,ゴウリシャンカー[ガネッシュ,ゴウリシャンカー] [Ganesh,G.]
フランス国立科学研究センター(CNRS)主任研究員、博士(工学)。産業技術総合研究所(AIST)、ATR脳情報通信総合研究所客員研究員。JST ERATO稲見自在化身体プロジェクトシステム知能・神経機構グループグループリーダー
岩田浩康[イワタヒロヤス]
早稲田大学理工学術院学術院長補佐/創造理工学部教務主任/総合機械工学科教授、博士(工学)。早稲田大学グローバルロボットアカデミア研究所所長/フロンティア機械工学研究所副所長兼担。日本バイオフィードバック学会理事、日本コンピュータ外科学会評議員、バイオメカニズム学会幹事。株式会社INOWA取締役CTO、株式会社オムテック取締役CTO、株式会社ROCK&LOTUS取締役CTO。JST ERATO稲見自在化身体プロジェクト自在化身体構築グループグループリーダー
杉本麻樹[スギモトマキ]
慶應義塾大学理工学部情報工学科教授、博士(工学)。JST ERATO稲見自在化身体プロジェクトバーチャル身体構築グループグループリーダー
笠原俊一[カサハラシュンイチ]
株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所リサーチャー。東京大学先端科学技術研究センター身体情報学分野特任助教、博士(学際情報学)。JST ERATO稲見自在化身体プロジェクト研究員
瓜生大輔[ウリュウダイスケ]
東京大学先端科学技術研究センター身体情報学分野特任講師、博士(メディアデザイン学)。JST ERATO稲見自在化身体プロジェクト研究総括補佐(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
蕎麦
モート
KOBAYASHI
ニッポニテスは中州へ泳ぐ
中村蓮