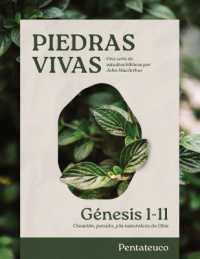内容説明
いまこそ、伝えたいあの戦場体験!トラック島、数少ない元兵士が語る、戦場の日常、非業の死、食糧難…反骨の俳人は、どのように戦後を生きいまを見るのか?
目次
プロローグ とても、きな臭い世の中になってきた
第1章 あまりにも似ている「戦前」といま
第2章 「死の最前線」で命を拾う―トラック島にて
第3章 捕虜生活で一転、地獄から天国へ
第4章 日銀は仮の宿、“食い物”にして生きてやる
第5章 明日のためにいまやっておくべきこと
著者等紹介
金子兜太[カネコトウタ]
俳人、現代俳句協会名誉会長、朝日俳壇選者。1919年、埼玉県生まれ。旧制水戸高等学校在学中に句作を始める。43年、東京帝国大学経済学部卒業。同年、日本銀行に入行する。44年から終戦まで、海軍主計中尉、後、大尉として、トラック島に赴任する。復員し、日本銀行に復職。62年、俳誌『海程』を創刊し、主宰。新しい俳句の流れを起こす。74年に日本銀行を退職。83年、現代俳句協会会長に就任。87年、朝日新聞の朝日俳壇選者。88年、紫綬褒章受章。2005年、日本藝術院会員。2008年、文化功労者。2010年、毎日芸術賞特別賞、菊池寛賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
96
戦争体験者と戦場体験者がいると思う。空襲や原爆も戦場と同じとは思うけど、遠く外地で食料の補給もなく、精神論だけで戦場に放り込まれて、やがて飢えや病気に苦しみ、手榴弾の誤爆で死んでゆくもの、戦闘機に撃たれる者、飢えで衰弱して死んでゆく者。著者もトラック島で体験し、戦友を見送った時のエピソードや、現在の日本憲法改正案や秘密情報に関することに警鐘を鳴らしている。本書には氏が詠んだ句 も載せられて居る。戦争を忘れた頃に戦争は必ず起きる。それは戦場体験者がいなくなった時かもしれない。図書館本2024/11/22
ちゃま坊
12
東大、日銀、トラック島の兵士、日銀、俳人という経歴。「アベ政治を許さない」という言葉が所々に出てくるが、アベノミクスのことではなく、安倍政権憲法9条改正問題の方だ。日本銀行と戦争国債のことが気になったが、これには触れていない。南洋諸島の戦争体験記は水木しげるを連想する。2025/10/11
tuko
5
俳人金子兜太氏が、自らの戦争体験を語り、あまりにも「戦前」に似ている今の日本に警鐘を鳴らす。目に見えない形で権力による統制が進み、権力が直接手を下さなくても、大きな権力に便乗して自分の鬱憤を晴らそうとする「下からの抑圧」という危険な事態が起こってくる。2016/09/29
海山ごはん
5
俳人の金子さんは、先の大戦中に南方のトラック諸島に赴任させられ多くの部下を亡くして帰還している。その前には、『治安維持法』によって投獄された俳句仲間の姿を見ている。日本が戦争へ傾く経過を見てきた、生き証人なのである。その金子さんが、今の日本の姿は戦前のそれに似ているという。先人の言葉は、重く受け止めたい。2016/09/07
kenitirokikuti
4
金子兜太は1919年生まれ、水戸一高から東大(いや東京帝国大学だ)、日銀に入り、1944年に海軍主計(将校)としてトラック島へ▲「新興俳句運動弾圧事件」。主要ターゲットは「京大俳句」。渡辺白泉「戦争が廊下の奥に立つてゐた」。金子は『土上』という雑誌に属していたが、主宰の嶋田青峰も治安維持法違反で投獄される。金子の先輩も特高に生爪を全て剥がされる。新興俳句は虚子の花鳥諷詠に対し、自然だけでなく人間社会も含めた。リアリズムという言葉が咎められた。近現代俳句史は他をあたろう2016/12/18