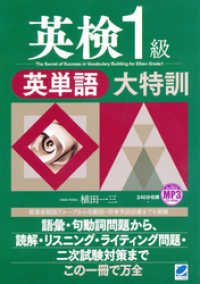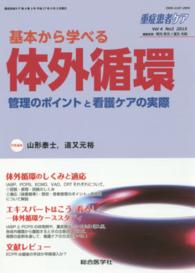出版社内容情報
文芸記者とは何者なのか?
日本に新聞が生まれておよそ150年。「国民新聞」に文芸欄を作った高浜虚子をはじめ、夏目漱石、国木田独歩、徳田秋声、菊池寛ら、多くの文学者が新聞社で記者をした。大正、昭和とつくる人と伝える人、文芸の職能はわかれ、記者の仕事も変わっていく。文学と密接に関わり、長きにわたって併走してきた文芸記者の仕事と生き方を追って、文学をめぐる環境がどうのように変わってきたかを探る。
本の雑誌好評連載「文芸記者列伝」を大幅改稿。補遺3本と文芸記者年譜を書き下ろし。明治中期の堀紫山(讀賣新聞)から令和5年の中村真理子(朝日新聞)、樋口薫(東京新聞)まで、二十四人プラスアルファの文芸記者の人生に迫る。
文学を商売にして世に定着させた功労者、ないしは戦犯、それこそが文芸記者である!
[目次]
はじめに──なぜ文芸記者なのか
一 論争と黒子の人 堀紫山(読売新聞) 12
二 振り回される人 嶋田青峰(国民新聞)20
三 怒られ通しの人 森田草平(東京朝日新聞)28
四 文学に踏み止まらない人 柴田勝衛(時事新報、読売新聞)36
五 庶民に目線を合わせた人たち 伊藤みはる(都新聞)43
六 記者をやめて花ひらいた人 赤井清司(大阪朝日新聞)50
七 最後まで取り乱さない人 渡辺均(大阪毎日新聞)56
八 威光をバックに仕事した人 新延修三(東京朝日新聞)63
八の補遺 文芸記者たちの雑誌刊行計画 70
九 クセのあるメンツに揉まれた人 高原四郎(東京日日新聞)79
十 騒がしい文化欄をつくった二人 平岩八郎、頼尊清隆(東京新聞)85
十一 文学の道をあきらめた人 森川勇作(北海道新聞)92
十二 自分で小説を書きたかった人 竹内良夫(読売新聞)100
十三 恥かしそうに仕事した人 田口哲郎(共同通信)107
十三の補遺 小説を書く文芸記者たち 114
十四 書評欄を変えようとした人 杉山喬(朝日新聞)124
十五 大きな事件で名を上げた人 伊達宗克(NHK)132
十六 多くの作家を怒らせた人 百目鬼恭三郎(朝日新聞)140
十七 エッセイでいじられる人 金田浩一呂(産経新聞、タ刊フジ)147
十八 出版ビジネスに精通した人 藤田昌司(時事通)154
十九 長期連載で鍛えられた人 井尻千男(日本経済新聞)162
二十 郷土で生きると決めた人 久野啓介(熊本日日新聞) 171
二十一 断定を避けた人 由里幸子(朝日新聞)178
二十二 生身の人間を大事にした人 小山鉄郎(共同通)185
二十二の補遺 賞を受ける文芸記者たち 194
二十三 面の皮が厚い人 鵜飼哲夫(読売新聞)200
二十四 いまの時代を生きる人たち 各社の現役記者 208
文芸記者年表 216
内容説明
芥川・直木賞がすごいわけじゃない!文学賞にニュース価値あり、とまつり上げてきた文芸記者こそが異様なのだ!日本に新聞が誕生して百五十年、文学と密接に関わり、長きにわたって併走してきた文芸記者の仕事と生き様を追い、文学をめぐる環境がどう変わってきたかを探る、まったく新しい文学史。
目次
論争と黒子の人―堀紫山(読売新聞)
振り回される人―嶋田青峰(国民新聞)
怒られ通しの人―森田草平(東京朝日新聞)
文学に踏み止まらない人―柴田勝衛(時事新報、読売新聞)
庶民に目線を合わせた人たち―伊藤みはる(都新聞)
記者をやめて花ひらいた人―赤井清司(大阪朝日新聞)
最後まで取り乱さない人―渡辺均(大阪毎日新聞)
威光をバックに仕事した人―新延修三(東京朝日新聞)
クセのあるメンツに揉まれた人―高原四郎(東京日日新聞)
騒がしい文化欄をつくった二人―平岩八郎、頼尊清隆(東京新聞)
文学の道をあきらめた人―森川勇作(北海道新聞)
自分で小説を書きたかった人―竹内良夫(読売新聞)
恥かしそうに仕事した人―田口哲郎(共同通信)
書評欄を変えようとした人―杉山喬(朝日新聞)
大きな事件で名を上げた人―伊達宗克(NHK)
多くの作家を怒らせた人―百目鬼恭三郎(朝日新聞)
エッセイでいじられる人―金田浩一呂(産経新聞、夕刊フジ)
出版ビジネスに精通した人―藤田昌司(時事通信)
長期連載で鍛えられた人―井尻千男(日本経済新聞)
郷土で生きると決めた人―久野啓介(熊本日日新聞)
断定を避けた人―由里幸子(朝日新聞)
生身の人間を大事にした人―小山鉄郎(共同通信)
面の皮が厚い人―鵜飼哲夫(読売新聞)
いまの時代を生きる人たち―各社の現役記者
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
メイロング
Shun'ichiro AKIKUSA
ウチ●
青いランプ