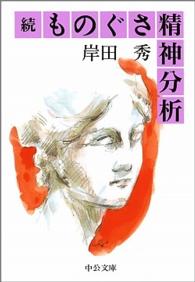内容説明
1921年発行の五セント白銅貨を集める男の目的とは?シカゴへ来た青年が巻き込まれる奇妙な犯罪+作者からの「公明正大なる」挑戦状。
著者等紹介
キーラー,ハリー・スティーヴン[キーラー,ハリースティーヴン] [Keeler,Harry Stephen]
1890‐1967。アメリカ、イリノイ州シカゴ生まれ。鉄工所で働きながら小説の執筆に精を出し、雑誌編集者を務めた事もある。1924年に初の長編少説“The Voice of the Seven Sparrows”を発表し、本格的な作家活動を開始。30年代の人気絶頂期には作品の映画化もされたが、やがて人気は下火となっていく。前衛的な作風が特徴的であり、多数の長編を遺した
井伊順彦[イイノブヒコ]
早稲田大学大学院博士前期課程(英文学専攻)修了。英文学者。トマス・ハーディ協会、ジョウゼフ・コンラッド協会、バーバラ・ビム協会(いずれも英国)各会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hanchyan@そうそう そういう感じ
35
読友さんからのおすすめ本。いやあ。面白かったよ面白かったけどこれがまた感想がなかなか難しい代物で(笑)。例えば「ジャンプなんかの新連載で、デッサンは狂ってるわ筋立てはご都合主義に終始してるわ等々で12週後には終わっちゃったけど、なんかやたら印象に残ってる作品」のような感じか。解説で「(笑)」連発しつつ指摘してるようになにもかもが中途半端!(笑)。ただなあ。またなんとも、ワイルダー映画の様にそこはかとなくチャーミングなんだよなあ。…こんな中途半端なレビューでご紹介元は納得してくれるんだろうか!?(笑)2016/05/20
Kouro-hou
26
あの論創社すら「説明不要の怪作」と言い切る1930年代Z級パルプミステリ。著者に関しては柳下毅一郎氏のサイトに詳しく紹介されていたり。つまりカルトな鬼才です。本作は巻き込まれ型サスペンスであり、殺人事件の謎を解く話ではありますが、普通のミステリを読みたい方はこんな沼に来てはいけませんw 著者はミステリを独学の独自解釈で書いており、やっぱり独学独自解釈したサスペンスに接合し、結果として基礎から狂った異世界の構造物になってます。が、それが信念に支えられたアートの域まで行っているんですね。ヒドイ内容。でも光る。2016/01/06
garth
15
思いつきのプロット、怪しい東洋人、でたらめな偶然……つまり、いつものキーラーである。「つまらない」という感想を見てしまったせいで読むのが遅れてしまったんだが、日本でぼく以上にキーラーのことをわかっている人間なんていないんだから、他人の感想に煩わされることなくさっさと読めばよかった。もちろんつまらないしくだらない。そんなのわかりきってるだろ! だってキーラーなんだから。文句言う人は普通の面白いミステリ読んでればよろしい。なお、「読者への挑戦」はたまたま直前にクイーンかなんか読んで真似してみただけと思われる。2015/12/05
飛鳥栄司@がんサバイバー
6
いい意味でも、悪い意味でもダマサれた。4分の3を過ぎたあたりで、挿絵に悪魔みたいな人がいて、公明正大なる作者からの挑戦を謳っているのです。お馴染みの読者への挑戦かと思いきや。思いもよらない結末に、壁本にしようかと思ったくらいだけど、冷静に考えてみてこれはある種の読者への挑戦であって、それにまんまと引っかかった自分に気がつくわけです。そして読後に残るのは作品に対しての心からの笑いとミステリに対しての苦笑い。こんな体験を現代で海外の古典ミステリでさせてもらえるなんて。というわけで、心を広くしてお読みください。2015/06/26
きゅー
5
「史上最低の探偵小説家」という称号を耳にしたうえで手に取った一冊。犯人を当てることなんて不可能だし、その動機もわけ分かんないけど、スピード感があって楽しい読書だった。ありえない偶然が何度も重なって主人公がハッピーエンドなのも気にしない。後書きで翻訳者がさんざん本書をコケにしているのも愛情の裏返しなのだろう。ただし、何も知らずに本書に手を出した人には「ご愁傷さまでした」と伝えたい。2024/12/10
-

- 和書
- 消防白書 〈令和6年版〉
-

- 和書
- 季節風 〈春〉 文春文庫