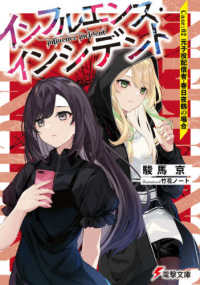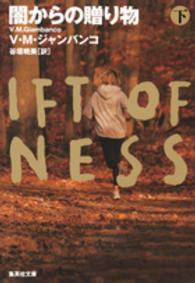内容説明
数々の作品を論じることによって現れる「日本人」「日本語」「日本文学」なるものの位置と、異文化・異言語への接触の倫理性。台湾で「日本語教師」をする著者が描く渾身の文芸評論。
目次
はじめに 日本語が栄えるとき
第1章 ふるさととしての「島」
第2章 「文学者」としてのリービ英雄
第3章 研究と創作の主体
第4章 中心と周縁
第5章 複数の声たち
第6章 ポストモダン時代の日本語文学
おわりに 3.11以後の日本語
著者等紹介
笹沼俊暁[ササヌマトシアキ]
1974年静岡県生まれ。2004年筑波大学大学院博士課程日本文化研究学際カリキュラム修了(学術博士)。台湾・慈済大学東方語文学系助理教授を経て、台湾・東海大学日本語文学系助理教授。専攻は日本近代文学・思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ルートビッチ先輩
1
台湾に幼少時代住み、日本にも住み、その後アメリカで日本研究を行いながらも日本語での創作を行うに踏み切ったリービ英雄を徹底的に<鄙>=マイノリティー性に向かう作家として取り上げ、その批評性を評価する。日本語=日本人という国民国家、グローバリズムにのっかるキャラクター小説とは異なるものとしてリービ英雄を言うために身体性や小ささに注目しているが、議論の中ではそれは反=◯◯としか提出されず、結局二項対立において批判されるべきものに寄っ掛かる議論になっている。その時の身体性とはどのようなものであり可能性があるのか?2015/07/15