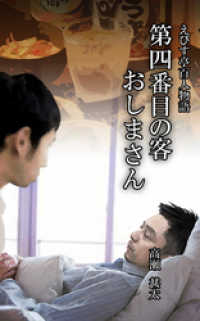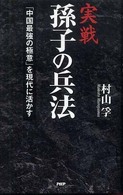内容説明
銭の前は米だった。米の前には石だった…賽銭本来の姿とは?賽銭を投げるわけ。人びとは賽銭にはどんな思いをこめたのか。賽銭にまつわるあれこれを、日本各地にたずね歩く。
目次
1 銭(お守りの銭;赤子と銭 ほか)
2 米(散米;お守りの米 ほか)
3 石(石を供える;赤子と石 ほか)
4 火の音(かしわ手;絵馬 ほか)
著者等紹介
斎藤たま[サイトウタマ]
1936年、山形県東村山郡山辺町に生まれる。高校卒業後、東京の本屋で働く。1971年より民俗収集の旅に入る。現在、秩父市在住(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
林克也
3
壺の献金問題が燃え盛る中、神仏への「献金」として、さていったい賽銭とは何だろうと思い手に取った本。まず驚いたのが斎藤さんのフットワーク。日本全国津々浦々でフィールド調査を行い記録を残したそのパワー。民俗学者というより、見たい知りたいという純粋な興味がその元になっている。次に、ものの名前とか行事の呼び名や方法に、全国各地で独自なものではなく、かなり共通な部分があるということ。続けてもう少し斎藤さんの本を読んでみたい。あと、これは出版社の問題だろうが、県名と郡・市町村とが合っていない個所が所々目についた。2022/09/03
きのたん
3
とにかく細かくバラまくことが肝心らしい。古くは石でもよい。来たしるしということなら額は数えない。硬貨の枚数は最小限参拝数だな。2020/12/08
reur
0
賽銭は神様に納めるのに何故放り投げるのか?という素朴な疑問から人が生まれてから死ぬまで魔物や災厄から身を守りたいと思って色んなモノに祈念してきたその時代時代の必然と長い歴史の流れで本質から遠ざかったりそのままの姿を残していたり 日本人がどういう考え方を持って生きてきたのかも感じられる興味深い内容でした。ただし、取材したお話しは原文のままで構わないんですが表現として標準語なのか方言なのか調べるにも難儀することばも多い為そこは出版者側にもっと考慮頂きたいところです。2012/01/29