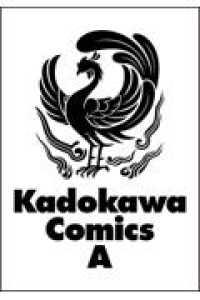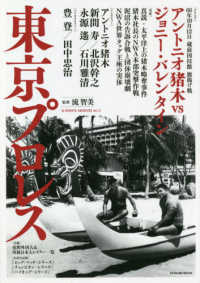- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(海外)
内容説明
バフチンの「ポリフォニー」、「カーニヴァル」といった概念、スターリン体制によって切断されたロシア・アヴァンギャルドと「銀の時代」の歴史的な連続性、ナボコフと「亡命」という見取り図。文学と芸術という文化の背景に潜む思想をあざやかに暴き出す。
目次
第1部 身体・声・笑い―ロシア文化のなかのバフチン(引き裂かれた祝祭―バフチンのカーニヴァルにおける無意識、時間、存在;現代ロシアにおけるバフチン―ポストモダニズムと文化研究のなかで;身体、声、笑い―ロシア宗教思想とバフチンの否定神学的人格論 ほか)
第2部 複数性の帝国―近現代ロシア文化史を読み直す(ロシア文化史の新しい見方―A・エトキント、B・グロイスの文化史研究を中心に;消去された自然―ロシア文化のディスクールにおける欲望と権力;「何もない空虚のなかで…」―近代ロシアにおける「音」の支配 ほか)
第3部 暗闇と視覚イメージ―ナボコフについて(ナボコフのロシア;ナボコフあるいは物語られた「亡命」;虚構の共同体―ナボコフ『ロシア美人』 ほか)
著者等紹介
貝澤哉[カイザワハジメ]
1963年東京生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。早稲田大学文学学術院教授。ロシア文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ecriture
9
ナボコフのとこだけ。ナボコフ作品を「失われたロシアへの望郷」と捉えるときの「ロシア」は空虚なものであり、19世紀末から20世紀初頭のロシアを改めて見つめ直すと、ナボコフのロシア在住時に既にしてロシアが失われていたことが明らかとなる。「ロシア」・「ロシア文学」と「私」の関係性を言葉という形式によって捉え直す試みがナボコフにとっての創作であり、「美しい追憶のロシア」は存在しない。他に、記憶と忘却、細部とずれ、視覚と聴覚などの分析がある。問題意識がクリアでキレのある文章。2011/11/03
nukuteomika
1
バフチンやナボコフの従来の評価の再検討。重複は多いが、宗教思想などロシア独自の文化に即した分析で興味深い2010/07/02
工藤 杳
0
深い射程、厳密な思考、それゆえの難解さ。2018/04/26