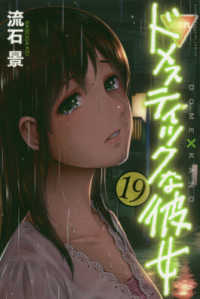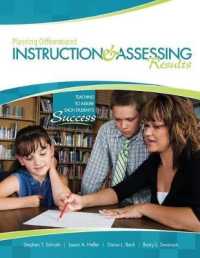内容説明
吸血鬼、ゾンビ、人狼、悪魔憑き、人造人間、スペースモンスター、幽霊、その他の名もなき怪物たちが、なぜわたしたちの心を掴んで離さないのか分析美学の第一人者である著者が、フィクションの哲学、感情の哲学、ポピュラーカルチャー批評を駆使して、その不思議と魅力の解明に挑む!ホラーの哲学の古典、待望の邦訳。
目次
第1章 ホラーの本質(ホラーの定義;幻想の生物学とホラーイメージの構造 ほか)
第2章 形而上学とホラー、あるいはフィクションとの関わり(フィクションを怖がる―そのパラドックスとその解決;;キャラクター同一化は必要か)
第3章 ホラーのプロット(ホラープロットのいくつかの特徴;ホラーとサスペンス ほか)
第4章 なぜホラーを求めるのか?(ホラーのパラドックス;ホラーとイデオロギー ほか)
著者等紹介
キャロル,ノエル[キャロル,ノエル] [Carroll,No¨el]
アメリカ合衆国の哲学者・美学者。1947年生まれ。ニューヨーク市立大学大学院卓越教授。元アメリカ美学会会長
高田敦史[タカダアツシ]
1982年生まれ。2008年東京大学総合文化研究科修士課程卒業。専門は、美学、特にフィクションの哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
14
幽霊だの呪いだのを全く信じてはいないが怖い話は大好きなのでホラーについての哲学的な考察はとても興味深く楽しく読めました。人間が進化する上で恐怖という感情がどのように発生&発達してきたのかということを知った上で能動的に恐怖心を得ることが娯楽になっている現状を眺めてみると面白いな。恐怖に限らず人間は感情を揺さぶられると快感なのかもしれない。弱い刺激は快感であり強い刺激は苦痛だと言うけれど、恐怖という感情も同じなんだろうな。2022/10/26
佐倉
11
存在しないものをどうして恐れるのか。どうして不快なものに惹かれるのか。この問いに90年代までの主にモンスターホラーを例として記述していく。辿り着いた結論はシンプルだがそこに至るまに様々な仮説を「あるタイプの作品には適用できるがすべてのホラーには適用できない」と検証する流れが頁の多くを占めている。SFや他のジャンルの創作にも援用できそうな分析(特に登場・発見・確証・対決の組み合わせについてなど)もあった。文化の境界にある不浄を求め、隠されたものを知ろうとする欲求。確かにホラーだし別のジャンルにも適用できる。2022/11/24
内島菫
9
本書では、ホラーの定義やホラーのプロットの特徴とともに、なぜ人はフィクションであるホラーを怖がるのか、なぜ人は拒否感を与えるものを含むホラーを求めるのか、という二つのパラドックスへの答えが探求されている。が、そもそも、なぜという理由を求める問いの立て方自体が、私は本書を少々ありきたりなものにしてしまっているように思われる。理由が求められたとき、その解答に何か目新しかったりわかりにくかったりするものが含まれていると、さらにその解答への疑問がわき、ではなぜその解答なのかと問いたくなる。2024/07/16
owlsoul
8
ホラーとは、危険かつ不浄なものに対して人間が感じる恐怖と嫌悪の入り混じった感情である。不浄とは、自然や社会のカテゴリーを逸脱したものであり、道徳的に禁じられたものだ。それら「禁忌」に対する好奇心が、ホラー的魅力の源泉となる。社会の混乱や不安はホラー表現に影響をあたえ、大恐慌のときには疎外された悲しきモンスターが流行し、共産主義への恐怖は謎の生物や異星人による寄生・侵略という形で表現された。そして現代、ポストモダニズムは人間を「肉」に還元し、その結果としてスプラッター的な人体破壊描写が多用されるようになる。2022/11/12
らむだ
6
ホラーを“アートホラー”と定義し、なぜ人は不快なはずのホラーに惹かれるのか、作り物であるホラーを怖がるのかという疑問を解消していく力作。良い意味でマニアらしさが抑えられ客観的にまとめられている。2023/03/19
-

- 洋書
- Visioni