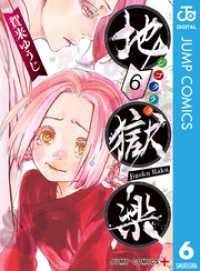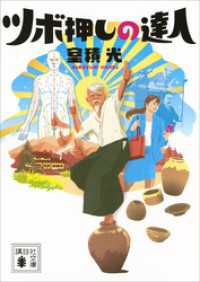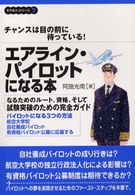内容説明
男性が変われば世界全体をより良い場所にできるはず。ターナー賞アーティストであり異性装者(トランスヴェスタイト)としても知られるグレイソン・ペリーが、新しい時代のジェンダーとしなやかな男性のあり方を模索する―。
目次
序 壊れてないなら直すなよ
1 魚に水のことを聞く
2 男性省
3 ノスタルジックマン
4 客観主義という殻
結 男たちよ、自分の権利のために腰を下ろせ
著者等紹介
ペリー,グレイソン[ペリー,グレイソン] [Perry,Grayson]
1960年イギリス生まれ。男性。さまざまな賞を受賞しているアーティスト(2003年にはターナ賞を受賞、大英博物館やサーペンタイン・ギャラリーをはじめ、日本でも2007年に金沢21世紀美術館で個展を開催。現代社会を風刺した、陶芸やタペストリー、彫刻、版画といったメディアの現代アート作品で知られる)。英国アカデミー賞受賞テレビ番組の司会者。リース・レクチャーの講師。ベストセラー作家(著書に『Playing to the Gallery』など)
小磯洋光[コイソヒロミツ]
1979年東京都生まれ。翻訳家。イースト・アングリア大学大学院で文芸翻訳を学ぶ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
R
42
男らしさという前時代的な価値観の滅びと、それにより困るであろう人々、世界を哀れむでもないが、語った本でした。ステレオタイプな男らしさというもの、その価値観というのがそういう人たちが作ったものであり、またそれを目指すことで窮屈な生き方になっている男の多さ、泣かされる女の多さ、それは世界のゆがみではないかと思わされる内容でした。世界が多様性という価値観を見出して、古臭いそれこれは滅びていくであろう、その哀惜も見えるようでありました。2020/05/26
ホークス
37
2019年刊。世界を牛耳る男性的価値観を疑い変えてゆく。著者はこの問題に長く苦しみ、本書は参考になった。以下自分用メモ。⚫︎攻撃的、理性的、感情的、協調的等はあくまで個人の資質。⚫︎「当然、常識」にジェンダーの毒が潜む。女性が働きやすく、女性管理職が増えれば平和的な改善を望めるし、男性も職場への隷属が緩む。⚫︎大切なのは男性的か女性的かでなく「人間的」。その内容をよく考える。⚫︎支配欲と依存欲にとってジェンダーは都合のいい聖典。⚫︎男性が刷り込まれた目的至上、組織至上の呪いに加担しない。利用しない。2025/04/26
マリリン
35
ジェンダーを男性の別視点から書かれているのが面白い。性差別を感じているのは男性も然りだとは意外だったが当然かも。 「4.客観主義という殻」の《性衝動とジェンダーにおける力関係》は、女性では理解できない部分もある。 著者が挙げる男性の権利=傷つく・弱くなる・間違える・直感で動く・わからないと言える・気まぐれでいい・柔軟でいる・これらを恥ずかしがらない... ふと思った、男性が訳もなく激怒する背景には刷り込まれた「男性性」があるのか...と。本書は2019年発行。「男性性」はあまり意識していないが男性は如何。2020/09/21
shikashika555
33
むむ。お国柄の違いは文化の違い。 楽しみにしてたけど、自分が目にする現実とは随分違う実例が多く、イマイチ乗り切れずに読了。2020/06/19
nbhd
18
著者がいう「デフォルトマン」というのは、ややっこしい男だ(定義的には白人・ミドルクラス・異性愛者を指す)。まず自分に疑問を持たず、オレがスタンダート。しかも「男らしくあれ」と言っちゃう古い男性と違い、ある程度わきまえているから、よりややっこしい。思うに、LGBTとかの話にふれて「俺、そういうのわかってるから」って言うような(妄想だけど、筋トレしてそうだ)。でさらに、ややっこしいのが「デフォルトマンの内面化」。デフォルトマンの周辺の人が「あの人は正しい」として、ひるがえって自己嫌悪に陥る展開。人間って複雑。2021/01/21