内容説明
日常を挑発するイメージ編集術!マルチ・デジタル時代の多様な図像表現も、本書の「フォトモンタージュ」をルーツにしてスタートする。
目次
第1章 はじめに
第2章 最優先するメッセージ(ベルリン・ダダ;ジョン・ハートフィールド;プロパガンダ、広告と構成主義)
第3章 メトロポリス―未来のヴィジョン
第4章 驚異と平凡―シュルレアリスムの想像力
第5章 フォトモンタージュと無対象芸術
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
∃.狂茶党
13
駆け足で辿る、フォトモンタージュ。 図版多数で、眺める本としても楽しい。 原著初版は、週刊誌サイズだったらしく、そのためか本文と図版の位置関係が結構ずれてる。 ちょっとした歴史、第一次大戦から、第二次大戦の後まで、もう少し後の時代も、ポップアートなどが少し取り上げられているが、ダダ/シュルレアリスムの時代(とロシア構成主義)が、主な話題である。 『ダダ/ナチ』を読んでおいて良かったような気がする。 美術史の本。2023/08/26
子音はC 母音はA
4
ダダ、構成主義、シュールレアリスム等の芸術運動で創られたフォトモンタージュ作品を豊富に提示し読み解く。あとがきで訳者の岩本憲児が述べてたがこの領域はあまり日本で取り扱っていないので貴重。もっとこの手法のやばさが認知される事を願う。2014/08/18
dilettante_k
2
原著は96年改訂版。1835年のタルボット「フォトジェニック・ドローイング」以降、ストレートフォトとパラレルに展開したフォトモンタージュ・コラージュ史を、特に多用したダダ、構成主義、シュルレアリスムを中心に、80年代前半までを射程にたどる。モノクロだが200超の図版を収録しており、視覚的に変遷が追いやすい。3者の方向性により「使用法」は異なるが、フォトモンタージュが絵画ほかに比べ比較的容易な技法であるため、文学者など「素人」まで作品の裾野が広がったことで、多様な展開を見せたことは特筆しておくべきだろう。2014/02/15
"Я"yo
0
良い本すぎ2012/10/25
KinugawaNZ
0
良い本すぎ
-
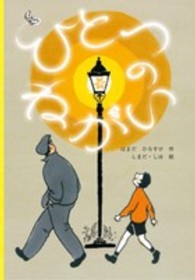
- 和書
- ひとつのねがい







