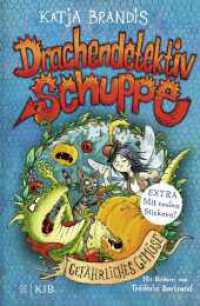内容説明
大学新卒採用の蔵人は、なぜ24時間勤務を笑顔でこなすのか。早朝出勤、長時間労働、肉体労働、少ない休日、宿直あり。それでもここには働く喜びがある。人気企業ランキングからは見えてこない、不況しか知らない世代のもう一つの潮流、新しい価値観、そして未来と希望。
目次
序章 “斜陽”の次にくる“夜明け”
第1章 “伝統”と“ものづくり”の復権
第2章 “伝統”を守り、“旧習”を壊す
第3章 “脱・季節労働”の雇用システム
第4章 “脱・職人気質”の組織づくり
第5章 “脱・匠”のものづくり
終章 これからの時代の“成功モデル”を目指して
著者等紹介
山本典正[ヤマモトノリマサ]
平和酒造代表取締役専務。1978年、和歌山県に生まれる。京都大学経済学部を卒業後、東京のベンチャー企業を経て実家の酒蔵に入る。大手酒造メーカーからの委託生産や廉価な紙パック酒に依存していた収益構造に危機感を覚え、日本酒業界にあっては他に類をみない革新的組織づくりをするとともに、自社ブランドの開発・販売に力を尽くす。一方で、全国の若手蔵元と協力のもと、日本酒試飲会「若手の夜明け」を立ち上げ、2011年から代表をつとめる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
ちょっと一杯本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
めぐねい
4
紀土のあとに鶴梅ができたのかと思ってたらそうでなかったのね。安くて美味しいお酒が提供できるのはこういうわけがあったんや。会社を立て直したって簡単には言えるけど、ものすごい苦労をされていたんだな。諦めないって凄い。今の日本酒ブームの立役者であり、ほんといつ寝てるんやろって心配になるぐらい日本中を飛び回っていて、日本酒の良さを広めてくれている。私も影響を受けた一人やと思う。もっと広まるといいな。2020/12/09
まちなかのノコギリ屋根
4
和歌山県の平和酒造の専務さんの書かれた書籍。最初は日本酒産業に特化した物事を書かれているのかな?と思っていましたが、実際にはすべての職業に関連する変革を書かれているように私は取りました。私自身も零細企業の跡取りですが、納得できることもかなりありました。ただ、内容から先代社長さんとのギャップもあるように感じましたが、そこが詳しく書かれていないのが残念でした。2019/05/31
マギー
3
会社の人に借りた本。酒蔵の社長が自身の会社に対する考え方や日本酒の売り方を紹介している。杜氏の閉鎖的な風習を如何に打破すべきかを考えたり、ラベルが高級感を出しすぎると却って良いお酒が売れなったりなど、酒蔵ならではの悩みのはずなのに、どことなく別の業界でも抱えてしまいそうな悩みが盛り沢山。その時の流行りに乗りつつ、ノウハウを継承していくシステムの存在が、会社としては大事なのだろう。2015/03/10
ハムクルーズ
2
紀土無量山に目がない私にとってとても興味深い内容。専門技術を中心にした内容かと思いきや、その視点は高く、範囲、奥行きは広い。量産主義でない日本酒の製造を伝統的手工業、というか家業としての商売ではなく、継続的通年企業とした経営観点から確立を模索している。たとえば職人の育成、採用等に関するスキームなどは他業界の経営者にも参考になるはず。2018/01/07
shin1ro
2
初対面の山本さんの印象は理知的な情熱家。「すべての人に愛される酒でなくてもいい。ただし好きになってくれた人を裏切らない酒を造りたい」というクダリは、「一部の人に熱狂的に好まれるより、大多数の人に嫌われたくない」仕事に携わる自分からすると羨ましい限り。「たとえば先方(小売店)に不幸が生じたときに私の頭をよぎるのが、売り上げ減なのか、先方の痛みなのか、ということだ。後者を感じられる人とだけ、取引をする」とは何たる男気、何たる潔さ! 店頭で試飲販売している蔵人の皆さんの笑顔の訳が分かった気がしました。2015/06/13
-

- 和書
- イエスの福音にたたずむ