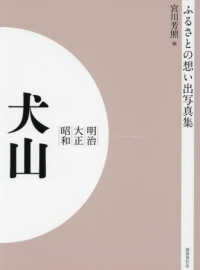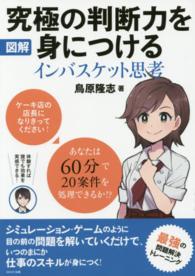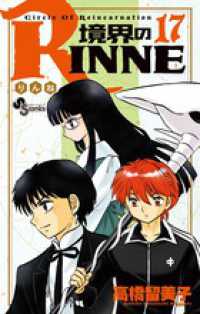内容説明
三越、高島屋、松屋、大丸、そごう―会社史の分析を軸とした、10年に亙る百貨店業史研究を集大成。
目次
先行文献の整理―百貨店業の会社史資料と戦前・戦後の百貨店業史研究(日本における百貨店業の会社史資料の整理;戦前日本の百貨店業史研究の整理と課題)
第1部 三越編(三井呉服店案内の裏面―『花ごろも』から探るマーケティング的経営組織の改革;営業部長日比翁助の模索―『春模様』から探る三井呉服店の経営方針;三越の成立と発展―先駆的百貨店の役割 ほか)
第2部 呉服系百貨店編(松屋の発展とその礎石―銀座の老舗百貨店の知られざる成立と発展;大丸の経営精神と専務取締役里見順吉―『大丸20年史』から探る経営法;高島屋の経営発展と飯田家―『高島屋100年史』から探る経営基盤 ほか)
百貨店業史研究の課題と方向性
著者等紹介
末田智樹[スエタトモキ]
1967年福岡県生まれ。岡山大学大学院文化科学研究科博士課程修了。現在、中部大学人文学部教授。博士(経済学・岡山大学)、博士(学術・昭和女子大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nishiyan
12
百貨店の成立の歴史を三越、松屋、大丸、高島屋、そごうの会社史分析を軸に解き明かした研究書。序章は先行文献の整理として百貨店業界研究の歴史を紐解いている。第1部は三越、第2部は松屋、大丸、高島屋、そごうを取り上げ、呉服店から百貨店への転換の歴史と戦前までの歩みから現在の各社の基礎が如何にして築かれたのかを解説している点は面白い。松屋の先駆性と高島屋の特異性には驚かされた。終章は今後の百貨店研究の課題について触れている。百貨店受難の時代、各社の保管する一次資料が散逸せず、研究に生かされることを期待したい。2022/05/09
NAGISAN
1
かつてあった三越大阪支店を思い出しながら、その章を読んだ。立地場所が悪い(昔の中心地)なかに佇む大正モダンな建物と、記述があったが外商の強い百貨店でした。地味が内容だが、誇りをもって勤めていた人たちの息遣いが感じられる本です。2022/09/13