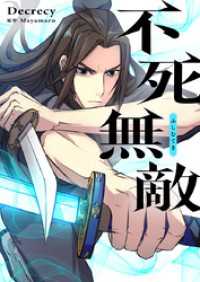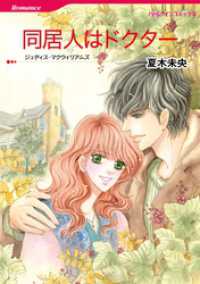目次
ようやくつくられた日本独自のお金
「三貨制度」とは何か?
世界的な金銀銅の資源国だった日本
三貨改鋳のホンネ
近代貨幣のめばえ1―紙幣使用の広がり
近代貨幣のめばえ2―円誕生の道
近代移行期のお金とは
著者等紹介
岩橋勝[イワハシマサル]
1941年、名古屋市生まれ。大阪大学大学院経済学研究科中退。1983年、経済学博士(大阪大学)。大阪大学経済学部助手を経て、松山商科大学(現松山大学)講師、助教授、教授、および社会経済史学会理事、同中国四国部会代表理事などを歴任。現在、松山大学名誉教授。日本銀行貨幣博物館の要請により、1999年、貨幣史研究会を立ち上げ、研究者人口の少ないこの分野のすそ野拡大に努めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
絵具巻
4
文京区立根津図書館で借りました。2016/04/26
犬養三千代
1
図録が多くて解りやすい❗良貨は退蔵され悪貨は流通して 悪貨のほうが経済を活発にする❗ほほう⁉2016/06/05
SK
0
107*「飛鳥時代~戦国時代」より複雑で難しく感じた。「金座絵巻」の全裸の男性たちが、胸を隠しているように見えるのだが(笑)。まさに「悪貨が良貨を駆逐する」エピソードが出てくる。日本は銀が豊富な国だったらしい。丹生羽書に「温故̪知新」が書かれていて面白い。このシリーズを読んでいると、経済に信用は大事なんだなと実感する。2016/04/26