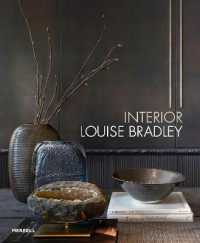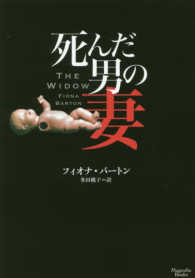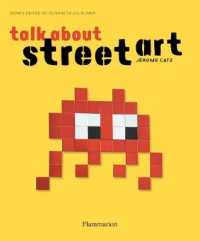内容説明
「ある」「いる」「おる」は、どういう点で共通し、どういう点で違うか。「権利がある」と「義務がある」との「ある」は、どのように違うか。「あらぬ噂」の「あらぬ」は、どういう意味で、どう成立したか。「ある」の未然形に打消の「ない」がつかないのは、どうしてか。「加計ありき。」の「ありき」は、どのようにして成立したか。…「ある」という動詞に関係する104項目の一つひとつのQとAとが、新しい発見と認識をもたらす。
目次
「ある」は、どのような事柄の認識で用いられているのか。
「ある」「いる」「おる」は、どういう点で共通し、どういう点で違うのか。
「ある」「いる」「おる」は、どう変換し、現在があるのか。
古典語「あり」が、いま、どうして「ある」であるのか。
「有る・在る」があるのに、どうして仮名書きされるのか。
「男ありけり。」の「ありけり」は、どう訳されているか。
人間を含めた動物の存在は、古典語では、どう表現したか。
人間の存在を「いる」に言い換えた事情は、何だったのか。
昔話の「あったとさ。」「おったとさ。」は、どちらが正しいか。
人間の存在を「ある」で表現する方言は、いまもあるのか。〔ほか〕
著者等紹介
中村幸弘[ナカムラユキヒロ]
昭和8(1933)年、千葉県生まれ。國學院大學文学科卒業後、昭和31(1956)年から15年間、千葉県立佐原第一高校・同県立大原高校・國學院高校に教諭として勤務。昭和46(1971)年、國學院大學専任講師・助教授・教授を経て、平成16(2004)年、定年退職。博士(文学)・國學院大學名誉教授。続いて弘前学院大学教授の後、平成19(2007)年から國學院大學栃木短期大學教授(学長)を務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。