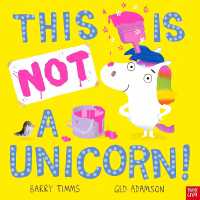- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > メディアファクトリー新書
内容説明
大きな角をもつカブトムシと、鋭い大顎のクワガタムシ。少年時代、彼らに熱中した男性は少なくないはずだ。カブト対クワガタ、またミヤマ対ノコギリはどちらが強い?意外にも研究が進んでいない彼らの生態を愚直に追い続けてきた孤高の研究者による意外性満載の最新レポート。進化論の研究が進んだいまだからこそわかる、カブトとクワガタのあまりにも面白い生態。
目次
はじめに 本当の自由研究は、大人になってから
第1章 メジャーでマイナーな研究対象
第2章 力のカブトムシ
第3章 技のクワガタムシ
第4章 持たざるものの闘い
第5章 空駆けるカブトムシ
第6章 メスの闘い
第7章 世界で翔ぶカブトとクワガタ
おわりに 臭いで辿る雑木林
著者等紹介
本郷儀人[ホンゴウヨシヒト]
動物行動学者。1977年、京都出身。琉球大学農学部卒業後、京都大学動物学の理学修士、理学博士を取得。カブトムシ・クワガタムシの闘争行動の研究を10年にわたり行っている。2008年、同大学のグローバルCOE(動物学教室)研究員となる。近年の研究では「ノコギリクワガタとミヤマクワガタの種間抗争」全244戦をビデオで撮影し、その勝敗と決まり手を調べ、「どちらの種が」「なぜ」勝っているかを解明。身近なクワガタムシにまつわる新発見として、話題になった(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
岡部敬史/おかべたかし
89
カブトムシはクワガタに圧勝するので、クワガタをとりたいのであれば、カブトムシが出現するピークの7月後半から8月前半を避けるといいそうだ。クワガタは多種で「東ノコギリ 西ミヤマ」という分布があることを知り写真に撮りたくなった。知らないことを知るのは楽しいなー。2018/07/18
ヨクト
18
皆さんご存知、虫の王様ムシキングといえばカブトムシ。子供に限らず、大人も魅了するカブトムシ・クワガタムシですが、その生態の研究はあまり進んでいないそうなのです。ミヤマVSノコギリはどっちが強い。カブトムシの争い。大きさをこえる子孫をのこす戦略。メスも闘う。交尾に見られる性格の違い。本書では、特にカブトムシ・ノコギリ・ミヤマクワガタを取り上げています。これ知っとけば世の虫取り少年達に自慢できるぜ。さぁ、夏が楽しみになってきた。2013/04/16
hry
3
期待以上に面白い内容だった。生物学の知識がない自分でも楽しく読めた。体が大きい個体にはそれを活かした戦略が、小さい個体にはまた別の戦略があるのが面白いと思った。餌となる樹液を、自ら樹皮を削って産み出す場合があるということに驚いた。実際に野生のカブト、クワガタを捕まえに行きたくなった。2013/07/26
まっし
3
これは今年の新書ランキング1位かもしれません。分かりやすい言葉で目からウロコという感じでした。そもそもカブトムシ、クワガタムシの研究がほとんどなされていないのは意外でした。カブトムシの角の大きさの秘密、ノコギリクワガタとミヤマクワガタの戦い、カブトムシとクワガタムシの交尾の際の違い、カブトムシの樹皮を削る行動など、本当に知らないことばかりでした。とりあえず雑木林に行きたいですね。2012/08/23
huyukiitoichi
3
予想以上にすごかった。『信じられないかもしれませんが、ワタシは雑木林内のカブトムシの交尾状況をほぼすべて把握していました。』は名言。2012/07/06
-
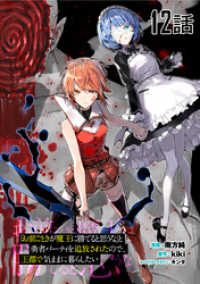
- 電子書籍
- 「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と…