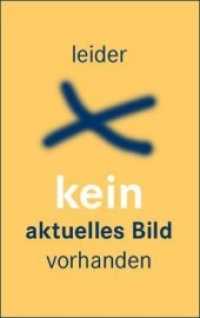出版社内容情報
最近の将棋は複雑化していてよくわからない、という声をよく耳にします。
しかし、あらきっぺ氏(元奨励会三段)は、将棋の基本的な思考は7つの理論で理解できるといいます。
強い人だけが感覚的に持っている概念や思考の道筋を論理的に分析する、渾身の将棋論!
自分の将棋観をアップデートするためにも、観戦ガイドとしても。
内容説明
最先端の感覚を言語化する―、これまでにない論理的将棋観。
目次
第1章 相対性理論
第2章 即効性理論
第3章 耐久性理論
第4章 可動性理論
第5章 保全性理論
第6章 局地性理論
第7章 変換性理論
著者等紹介
あらきっぺ[アラキッペ]
平成16年6級で森信雄七段門。平成28年三段で退会。奨励会退会後もアマチュアとして将棋の活動を続け、第42回朝日アマチュア将棋名人戦全国大会にて4位の成績を収める。並びに招待選手として出場した第13回朝日杯将棋オープン戦において、出口若武四段、大石直嗣七段を破る快進撃を見せた。将棋の普及にも熱心であり、著者が運営する「あらきっぺの将棋ブログ」はプロの将棋を独自の目線とわかりやすい語り口で解説し、人気を博している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
akihiko810/アカウント移行中
23
元奨三段・アマ高段ブロガーの著者が、現代将棋の「プロや高段者の思考法」を論理的に分析し言語化した本。 この本は凄い。将棋勝利思考法、つまりは「大局観」を言語化した本は初めてではないか。「手筋、次の一手」に出てきそうな妙手のパターン分類化に成功した。ただし、内容は高度なので初段程度ないと理解できないかもしれない。 現代将棋=囲いを手抜いて速攻・固さよりバランス重視 がなぜいいかを解説。金銀の連結「クリップ」(片美濃、エルモ、雁木の連結)、四駒方式(四枚の攻めは切れない。攻め駒3枚以下は駒の補充、2022/06/27
みんく
14
級位者のわたしでもおもしろかったー!基本の手筋から、現代将棋ならではの手筋まで、七つの理論に分類。豊富なプロの実戦をもとに解説してあり、分かりやすい。「さっさと桂を跳んで速攻」「堅い囲いより広さ」などの即効性理論の、現代将棋への影響は大きい。あとがきには「一昔前は特定の戦型の将棋ばかり指され、どことなく閉塞感が漂っていた」のが「現代将棋は多種多様」と、未来は明るい。AIの出現によって、先手がこう指せば必勝みたいな定跡ができ、将棋がつまらなくなるんじゃないかと危惧していたけど、全然そんなことなかった。2021/03/31
ま
13
近年は容易にプロの棋譜にアクセスでき、ある意味プロとアマチュアの物理的な距離は縮まったといえるが、棋力の差は加速度的に離れていっていると思う。本書は、プロが何を考えてその手を指したのか?というモヤモヤに一定の指針を示して答えたもの。「相対性理論」で味を占めたのか、○○性理論というネーミングに固執しすぎな印象。ただ、「クリップ」のワードセンスは素晴らしい。クリップは良い形だという認識は何となく持ってたけど、それをこれだけ言語化したのもすごい。土居矢倉や雁木の流行をこのクリップで説明したのには思わず膝を打った2021/02/15
Book Lover Mr.Garakuta
10
【図書館本】【速読】:将棋については知識不足で良く解らなかった。2021/12/25
⭐︎治栄⭐︎
4
お世話になっている方から将棋大会への参加要請を受けたため勉強のために再読し、昨日は有段者メンバーが集まるA級クラスへ参戦。その結果、なんと全勝優勝。この本で学んだAIによって従来の常識が塗り替えられた序盤と古き良き時代(?)に学んだ5筋位取り戦法をミックスしての快挙達成。本当にビックリした2025/03/16