目次
第1章 食事を考える枠組み(ある食卓の風景から;食事を考える枠組み)
第2章 食事の背景(「熱い食べ物」と「冷たい食べ物」;イスラームと食;食材:菜市場を歩く;調味料・道具:台所の風景)
第3章 食の風景(家での食事;信仰の場所での食事;料理店での食事)
著者等紹介
砂井紫里[サイユカリ]
早稲田大学イスラーム地域研究機構研究助手。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。文化人類学専攻。1997年から中国福建を中心にアジアの食事と食べ物についてのフィールドワークを行なっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
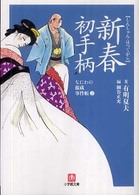
- 和書
- 新春初手柄 小学館文庫




