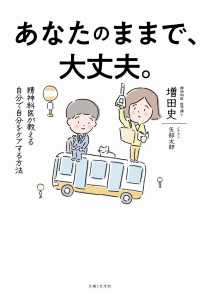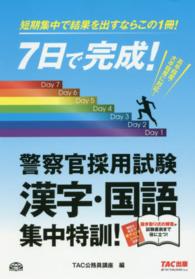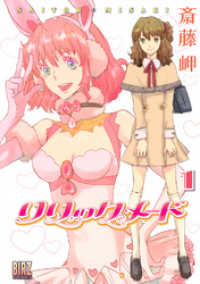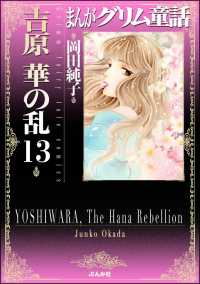- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
稲と米は、日本人にとって食文化の中心としてだけでなく、生活そのものになっています。田植えから稲刈りまで四季を通じて水田は、我々の原風景であり、収穫に関わる祭祀や年中行事も各地に多々催されます。わら・もみがら・ぬかなどの副産物も、衣食住に活用されてきました。今回の『YUCARI』は、とても身近だけど、まだまだ知っておきたいこともある「稲と米」です
今回の『YUCARI』の特集は、「稲と米」です。
日本人のお米へのこだわりは、とても強いものです。数々のブランド米が生まれ、お米マイスターがいる米専門店も話題になっています。「おいしいごはんを食べたい!」という人のために「お米の選び方・ガイド」を。甘さ・つや・粘り・食感・のどごし……、米職人に聞いた「お米のおいしい炊き方」も紹介しています。健康を意識される人には、精米による白米や5分づき、玄米などの分類、胚芽米や発芽玄米といった進化した加工米の話もあります。
しかし、日本人にとって、稲・米は主食としてだけでなく、古来、生活・文化・経済・政治とずっと関わってきたのです。特集では、米の文化的な側面にも迫ります。収穫を願い祝う祭祀が各地で行われ、石高による徴税制度が用いられました。大判小判といった日本独自の貨幣も米俵デザインです。わら、もみがら、ぬか。米の副産物も、先人の知恵で衣食住に活用されてきました。中には、卵を持ち運ぶ「つと」、おひつを囲う「いずみ」などのわら細工のように職人技に昇華されたものもあります。見事な作品は、誌面で見てください。
畦を駆けて遊ぶ子ども、のんびり立つ案山子、重そうに傾ぐ稲穂……、田植えから稲刈りまで、一年を通して田園風景は、我々日本人の脳裏に刻まれています。継承者不在、生産者減少が懸念されていますが、一方、棚田オーナー制度のように、米づくりを通して土地に受け継がれてきた文化・風習を次世代に伝えようとする動きも全国で広がりつつあります。お米の味だけでなく、水田や周辺の自然環境を意識した環境共生型の米づくりも各地で見られるようになりました。
私たちにとって身近な「稲と米」は、日本の大切なモノ・コト・ヒトの素晴らしさを改めて実感するのに、とてもいいテーマだと思います。
<特集内容>
・フォトエッセイ 棚田に魅せられて。
・日本人と稲作の関わり。
・トキと共生する米づくり。
新潟・佐渡島
・五ツ星お米マイスターに聞く! お米の選び方。
・米職人に聞く! お米のおいしい炊き方。
・ごはんをおいしくいただくお鍋とおひつ。
・古今東西 日本のごはんいろいろ。
ちまき/おこわ/なれずし/かて飯/お粥……
・稲の恵みいろいろ。
わら/ぬか/もみがら
・棚田を守りながら人と人の輪を広げてゆく。
・コラム=稲と米の基礎知識。
?@「イネ」とはどんな植物?
?Aお米の分類
?Bお米の炊き方・使い方事情
?Cお米の食べ方いろいろ