目次
服制の成立―縄文・弥生・古墳・飛鳥・奈良(腰蓑をつけ、獣皮をかけた婦人;貫頭衣の倭の婦人 ほか)
和様の創製―平安(女官朝服;公家女房、裙帯比礼の物具装束 ほか)
武装の伸展―鎌倉・室町・安土桃山(上流武家婦人通常の正装;つぼ装束にむしの垂れぎぬの旅姿 ほか)
小袖の完成―江戸(江戸時代前期の正装の公家女房;小袖姿の慶長頃の上流婦人 ほか)
洋風の摂取―明治・大正・昭和前期(皇族女子盛装;女官袿袴礼服 ほか)
著者等紹介
井筒雅風[イズツガフウ]
大正6年2月11日京都に生まれる。株式会社井筒取締役社長。財団法人宗教文化研究所理事長。風俗研究所主幹。風俗博物館館長兼学芸員。日本風俗史学会理事・関西支部長。学校法人京都成安女子学園理事長。京都女子大学講師。米国羅府オリエンタル大学名誉教授。文学博士。「原色日本服飾史」により日本風俗史学会第10回江馬賞。平成8年5月20日寂、79歳(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
茉莉花
55
やっぱり着物は良い~!!最高✨すごく細かく載っていて勉強になりました!タイムスリップして、自分の目でその時代の衣服について研究したい…(笑)2022/01/17
たまきら
40
おお~綺麗ねえ。とっても面白かったんですが、結構日本も東西で好みが違うし、どちらかというと京都方面のイメージなのかなあ…なんて思いながら眺めました。島原大夫だし…。いや、いいんですけどね。さすが京都にある風俗博物館だなあ。2024/08/22
Koning
32
古代から昭和初期までの日本の服飾の歴史を等身大人形(マダムタッソーの蝋人形を見てやらねば!と思ったそうで)に衣装を着せたものを展示する風俗博物館の所蔵品を使った「原色日本服飾史・増補改訂版」の女性に関する項目を再編集した本。フルカラーで写真はほんの判型が小さいのでちょっと小さいけれど、非常に美しく見応えがある。古代の推測ものはさておき、具体的に絵巻やら錦絵に残るあれこれが現物ではこう見えるというのがありがたい。資料的な感じだけれど、眺めてるだけでも楽しいです2016/06/13
ゆずきゃらめる*平安時代とお花♪
27
最近、よく平安時代前後の小説を読むので参考に。今回は平安時代の装束をじっくりと読みました♪女房装束は時代を考えても一番絢爛豪華です!また読みたい一冊。2018/11/19
鯖
20
こっちも面白い。後水尾帝の中宮和子の正装を復元した「江戸時代前期の正装の公家女房」などなど。事細かに説明があるんだけど、文の結びが「重量感に溢れている」でなんというか、文章も地味に面白い。奈良時代の女官は思ってたよりも動きやすそうで、ちょうど古代奈良の女性官僚に関する本を読んだところだったので、しみじみ納得したのでありました。平安時代、お転婆で庭を駆け回っていた定子の妹が入内して一年経たないうちに、脚が萎えて、走れなくなってしまったという小説を前に読んで、いたましさに泣いた。十二単は拷問だと思う。2015/11/21
-

- 電子書籍
- 離婚した元夫が私にゾッコンのようです【…
-

- 電子書籍
- 理想の彼女【タテヨミ】第57話 pic…
-

- 電子書籍
- Love Lesson~はじめて、全部…
-
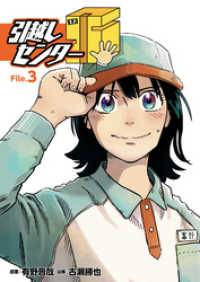
- 電子書籍
- 引越しセンターS 3 FOD
-
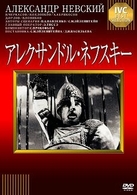
- DVD
- アレクサンドル・ネフスキー




