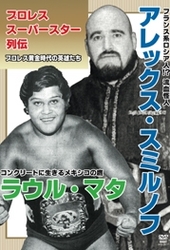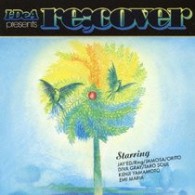内容説明
自分の中の「甘え」を断ち切り、ぶれない生き方の基準を持つ。
目次
「底辺」を広げると「高さ」が生まれる
壁は「壊して進む」
「人の支え」がある人
肝心なときに「助け」になるもの
「二流」に手を染めない
「がんばり力」を蓄える
「オリジナリティ」の強み
「地に足が着いた人」の力
何があってもへこたれない「復元力」
判断基準は「美しさ」
“画品をみがく”ように
「自分の色」を打ち出していく
いつも「キラリ」と光らせる
「底力」をつけてくれる本たち
人間としての「幅」
周囲に流されないために
人を「納得させる」もの
「すごい前進力」を生み出す法
著者等紹介
平山郁夫[ヒラヤマイクオ]
1930年広島県生まれ。東京美術学校(現東京藝術大学)日本画科卒業。前田青邨に師事。53年日本美術院展で初入選。59年「仏教伝来」が注目を浴び、61年「入涅槃幻想」により日本美術院賞(大観賞)を受賞。仏教と東西文化の交流、シルクロードをテーマに旺盛な創作活動を続ける。98年文化勲章受章。現在は、財団法人日本美術院理事長、日中友好協会会長、ユネスコ親善大使など国内外での要職多数。「文化財赤十字構想」の理念に基づき、世界の文化遺産、文化財を保存・修復する運動を促進している。東京藝術大学教授、美術学部長の後、二度にわたって学長を務め、若い人材への教育にも尽力(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Lara
99
著作時、70才代後半。毎日、広いアトリエを、他人に任せず自ら、掃除機をかけ、床の乾拭き30分。掃除をすることで集中力アップに役立てる。そして、一度アトリエに入ると三時間は集中し、それを一日に三度繰り返す。三時間が三十分に感じる。大好きなお酒は55才で止めた。粗衣粗食を心がけ、栄養剤、薬に頼らない。公的な仕事を抱えられながらも、毎日ご自身の作品のために、尽力される姿は、まるで修験者のよう。とにかく教養を学んで、積みなさいとおっしゃる。何と立派な、お手本のような人生。2021/05/18
Y2K☮
29
三度目の読了。過去二回はなぜかレビューを書いていない。精神論的な努力絶対主義が肌に合わなかったか、感謝を忘れず云々を成功者にありがちな建前論と感じたか。「ぶれない=変化しない」と解釈した可能性もある(少なくとも私は以前の己と矛盾することを成長の証と捉えている)。一方で頷ける点も多々ある。たとえば「すぐに役に立たないことのすすめ」や年齢に合わせた創作法。長い棒を振り回す力技から一刀両断の居合い抜きへというのは、小説へ落とし込むと長編から短編や掌編へと解釈できる。まさにいま取り組んでいること。背中を押された。2024/09/05
booklight
28
画家、平山郁夫の自己啓発本。この人でさえ若い頃は、何をしていいのかわからない、という悩みを抱いていた、というのだから驚く。被爆の後遺症で、体の調子も悪く、進退窮まった時に、無理してでも行った八甲田山スケッチ旅行。そこでの限界のなかで歩いた事自体が、強力な体験となり、イメージが降りてくる。そんな話と、底辺を広げると高さが生まれる、など小手先のノウハウでなく、まともなことをいっている。近道などなく、ぶれない、というのはつまり周りに左右されずに、しっかり底辺の力をためていくことが大事。こんな正論もたまにはいい。2024/12/08
はる
25
教養を身につけることは、専門を極めるためにも大切なこと。学生時代、幼少期に、地道にがむしゃらに本を読んだり絵を描き続けたりしたことが、後の力となる。一流のものに触れる、手探りでも自分の道を切り開く、など己の信じるものを貫き通すことの大事さ。生きていく上で、美しいと感じた。そのように仕事をしたいし生きていきたい。2020/01/04
橘 由芽
10
ぶれる。ぶれっぱなしである。そんな浮き草のごとき私に喝を入れていただけまいか、の気持ちで手にした一冊。「人間としての幅が大きいほど、なにが起ころうが立ち向かっていける。 ぶれない自分を形づくることができる。」スポーツでも芸術でも学問でもなんでも一見ムダだと思えるような地道な積み重ねがピラミッドの土台を広く安定したものにする。近道などない。2023/03/12
-

- 電子書籍
- 古都さんぽ1 ~写真家 茶谷明宏がゆく…
-

- 電子書籍
- ボッコちゃん