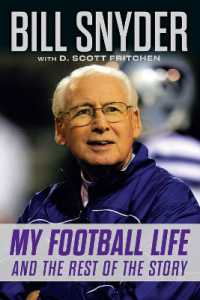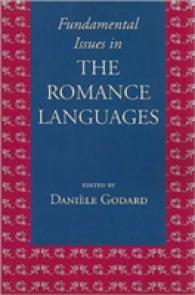- ホーム
- > 和書
- > 文庫
- > 雑学文庫
- > 三笠 知的生き方文庫
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェルナーの日記
120
孫武の残したと伝えられる『孫氏の兵法』を1.始計篇2.作戦篇3.謀攻篇4.軍形篇5.兵勢篇6.虚実篇7.軍争篇8.九変篇9.行軍篇10.地形篇11.九地篇12.火攻篇13.用間篇の13項目に分け、その中から著者の視点によって選定された引く敵に誰も知っている内容によって編まれた1冊。『始計篇』だも自らも”兵は詭道なり”と言っているように戦争はとどのつまり「騙しあい」であって、そこに善悪などない。もともと詭道(正道ではない道、ごまかしの道、権謀術数など智恵の限りを使って戦う道をいう)である。2017/01/29
ehirano1
112
13編の兵法を興味深く読みました。結構ドギツイ箇所もあり、読んでいるうちに戦わずとも何か平和的な解決手段はないのかなと平和主義者みたいになってきましたが、孫子の兵法の最大のポイントは『戦わずして勝つ』ですから、孫子も実は戦いに勝つための方法を考えに考え抜いているうちに戦が如何に割に合わないかに気付き、行き着いた戦法が実は『戦いをしないこと』、そしてなぜか『戦いをせずして勝つ』ことだったのかもしれないと妄想してしまいました。2020/12/12
ehirano1
86
「何事も下手な知恵をはたらかすよりは勢いに乗ることを考えた方が良い」から『組織や指導者は寧ろ如何にして集団の力を引き出すかに注意を向けるべきだろう』、と集団の力学へと応用できるあたりは孫子の兵法が経営戦略の書としても読める左証の1つではないかと思いました。2025/07/16
ehirano1
76
武芸者「何流か」、塚原ト伝「無手勝流だ。刀を抜くのは未熟な証拠である」。この返しで塚原ト伝が既に勝っているところが面白いです。無手勝流とか今思い付いたようなありもしない流派を言った後に、おまえは未熟、と説教しています。リアルでやれば大変なことになりますが、好戦的な人には「無手勝流」と言っておけばいいかもしれません。勿論その後に「ふざけんな!」と説教されるかもしれませんが・・・・・。2024/02/04
ehirano1
75
「必死は殺され、必生は虜にさる」を会社経営の戦略書に応用すると、「将師が必死になることよりも、むしろ部下を必死にさせることである。そこを配慮するのが将師の務めである」とことです。他書においても著者はこの事に折に触れて言及されています。将師(≒管理職)がプレーヤーになってしまって部門がガタガタになるケースは散見されますので、この言には共感しています。将師(≒管理職)の役割がわかっていない管理職が多い一方で、管理職もプレーヤーとならざるを得ない状況あるようで・・・・・うーーーーーん。2021/10/04
-

- 電子書籍
- 夫は不倫相手と妊活中【分冊版】 49 …