内容説明
1816年、琉球。琉球人との交流、温かく克明に描く新資料―バジル・ホールの『朝鮮・琉球航海記』を複眼的に見直す。
目次
日記 一八一六年(九月二一日土曜日;九月二二日日曜日;九月二三日月曜日;九月二五日水曜日;九月二七日金曜日 ほか)
解説 クリフォードの仕掛けた琉球・日本の近代
著者等紹介
クリフォード,ハーバート・ジョン[クリフォード,ハーバートジョン]
アイルランド生まれのイギリス人で、1816年9月15日頃から10月27日までのあいだ、英国海軍大尉として琉球を訪問している
浜川仁[ハマガワヒトシ]
沖縄キリスト教学院大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
himawari
7
首里城や、艶やかな漆塗りの上に輝く螺鈿細工が豪華な器、珊瑚で飾られた王冠などを生み出した琉球王朝に思いを馳せると確かに魅力的でロマンがある。二百年も昔に、琉球に語学調査に来たイギリス人の彼もまた、この訪琉記でヨーロッパに琉球ブームを起こしたらしい。取り分けて面白いエピソードは余りなかったが、読んでいると昔にタイムスリップして彼らの異文化交流を間近で見ているようでワクワクした。琉球料理やその当時の文化の高さも興味深い。なかなか上陸させてもらえない彼らイギリス人達と琉球の役人達との攻防も面白かったな。2016/01/05
トマズン
1
本書は、琉球を世(西洋)に知らしめたバジル・ホールの「朝鮮・琉球航海記」と同じ頃に書かれたものである。 (バジル・ホールは著者の親友でライラ号の艦長であった、著者はそのライラ号の乗組員である) 一切の公務から自由の身であった 著者の訪琉記には、のびのびとした気持ちと琉球人とのプライベートな交流が刻々と記されている。 彼の日記は琉球をより近くに感じるだけでなく 既に消滅した王国の言語が見られる最古の資料でもあり 歴史的に価値のあるものである。 ただ私的に思う、ベッテルハイムを遣したのはお前か と。2016/10/22
kan
1
阿片戦争、ペリーに先行する英国艦による琉球上陸日記。首里を王都とする琉球が垣間見えた。2016/02/01
ふら〜
0
すごく久々に読書メーターに記録。これからぼちぼち記録を復活させたい…というのは置いておいて、この本は19世紀前半に来琉したとある英国軍人の記録。沖縄の人々にとって耳障りの良いことが(バジル・ホールの記録と同じく)書かれてて、当時のイギリス人の考え方の一端も読み取れたり。2016/07/10
-
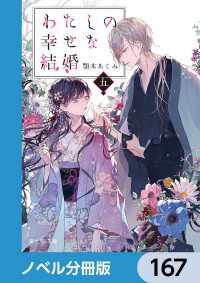
- 電子書籍
- わたしの幸せな結婚【ノベル分冊版】 1…
-
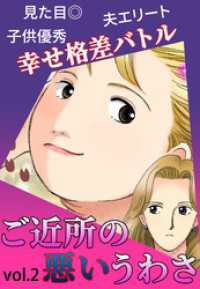
- 電子書籍
- ご近所の悪いうわさ Vol.2 ご近所…
-
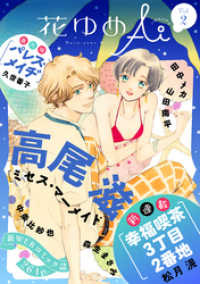
- 電子書籍
- 花ゆめAi Vol.2 花ゆめAi
-
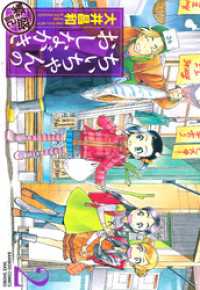
- 電子書籍
- ちぃちゃんのおしながき 繁盛記 (2)…





