内容説明
外からみえにくい障害である、流暢な日本語を話す聴覚障害者、中途失聴者の内的世界とその苦悩を見事に描き出した本書は、障害者への共感(相手の立場に立って心を観察する)のあり方への新たな方向性を提示してくれる。聴覚障害者だけでなく、難聴者の比率が増える超高齢者の世界を理解し、彼らへのコミュニケーションのあり方を考える上にも重要な示唆に富んだ名著。
目次
第1章 複雑な聴覚障害者の世界
第2章 コミュニケーション不全が引き起こす問題
第3章 中失・難聴者に起こりがちな反応や行動
第4章 多様な見えなさにつきまとわれる中失・難聴者
第5章 中失・難聴者と精神的危機
第6章 中失・難聴者がストレスなく生きられる社会とは
著者等紹介
山口利勝[ヤマグチトシカツ]
1955年広島生まれ。高校時代に聴覚の異常を感じ始める。1978年広島修道大学人文学部卒業後、大手自動車メーカーに勤務(92年退職)。1994年広島大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程入学。1999年同課程修了(心理学の博士号を取得)。2003年7月現在、第一福祉大学助教授。専門は発達心理学。聴覚障害者の心理社会的発達を主な研究テーマとしている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ナコち
6
「レインツリーの国」を読みこの事実を知り、今まで偏見や勘違いで捉えてきた誤りにこの本を読むことで気付けました。聴覚障がい者が皆、手話が堪能だという思い込み。それら様々なことをひとつひとつ考えを改めていかないとと思う。聴覚障がい者にとって問題ないコミュニケーションは筆談であるということ。それを忘れないようにしたい。2011/01/23
tora
6
健聴者が考えている聴覚障害者と実際の聴覚障害者の違い。このズレを認識することが必要。2009/09/11
newpapa
1
この本を読む前に著者の経歴を読んでいたので、より思い入れを持って本を読みました。途中失聴者と難聴者の違いをリアリティーを持って理解できたかというとまだまだですが、そこには大きな違いがあることを知りました。 2020/05/23
-
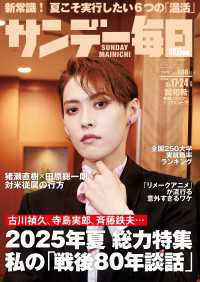
- 電子書籍
- サンデー毎日2025年8/17・24日…
-

- 電子書籍
- 【フルカラー】ヤミツキチュウ~私の人生…
-
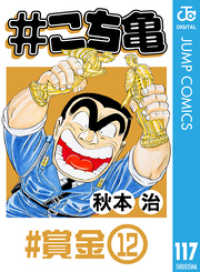
- 電子書籍
- #こち亀 117 #賞金‐12 ジャン…
-

- 電子書籍
- 異世界失踪調査局 ~異世界へ消えた人た…





