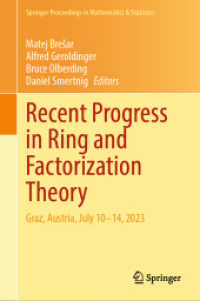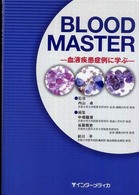出版社内容情報
900年も前の戦乱の最中、逆境から身を起こし、仏教と平和の精神、卓越した国際感覚をもって、新しい国家のかたちを模索した藤原清衡。「平泉研究」の第一人者が最新の研究成果を平易に紹介する。
内容説明
戦乱の最中、逆境から身を起こし、仏教と平和の精神、卓越した国際感覚をもって、新しい国家のかたちを模索した男がいた。それも、900年も前に、辺境・東北の地で。
目次
第1章 中尊寺落慶供養のビッグ・イベントにて
第2章 国づくりのはじめに立ち返って
第3章 東アジアのグローバル・スタンダード
第4章 ハイブリッドな新人類の誕生
第5章 修羅の前半生
第6章 大夫から御館へ
第7章 金色堂に死す
著者等紹介
入間田宣夫[イルマダノブオ]
1942年(昭和17年)宮城県涌谷町生まれ。68年東北大学大学院文学研究科国史学専攻博士課程中退、同年東北大文学部助手。山形大学助教授、東北大学教養部助教授、東北大学東北アジア研究センター教授などを経て、2005年に東北大学を定年退職、東北大学名誉教授。06年から東北芸術工科大学教授。10年4月に同大学大学院長、11年1月に同東北文化研究センター所長、13年4月に一関市博物館館長に就任。専門は日本中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
てん06
14
筆者の長年の研究の結果から、藤原清衡について自由に語った本という感じである。藤原清衡の伝記や評伝といったものとは違う。少し難しいが、じわりと面白い。2021/11/04
TheWho
14
元東北大学教授で、日本中世史を専門とする著者は、奥州藤原氏の初代清衡を言及する歴史読本。先に読了した今東光「蒼き蝦夷(えみし)の血〈1〉藤原四代 清衡の巻」と同じく武力ではなく、普遍的な哲学、宗教である仏教を用い、辺境の蝦夷の異郷と呼ばれた奥州を先進的な地域として発展させた業績を淡々と語っている。芭蕉の「夏草や兵どもが夢の跡」を思い浮かび、かつマルコポーロの黄金の都ジバングを彷彿とされる平泉文化を体現できる一冊です。2018/03/30
金目
8
平泉を仏国土の中心にしようとした、奥州藤原氏の初代清衡。修羅の前半生を過ごし、中尊寺を建立し、中央と密接に繋がりながら、京都を越えていこうという気概を持っていたことをうかがえる。現在中尊寺と言えば金色堂が想起されるが、そもそも清衡が建立した当時はいたって個人的なお堂だったであろうというのは意外。その後の平泉の運命をどこまで予想できていたのだろうか2022/05/05
たひ
2
藤原清衡についての本ということで、それほど内容も難しいということもないですし、大変参考になりました。ただ、個人的には少々飛躍しているというかこじつけ気味なようなところもあるような気もしてしまいました。
天茶
0
★★★★2020/05/26
-
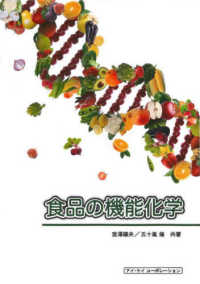
- 和書
- 食品の機能化学