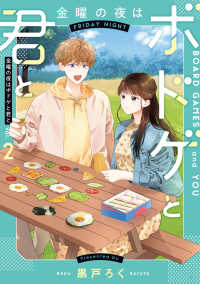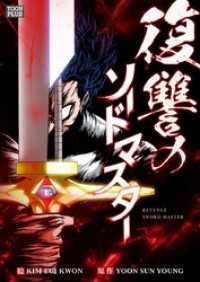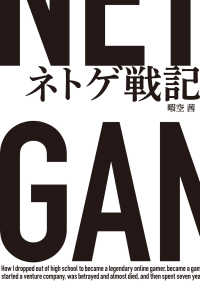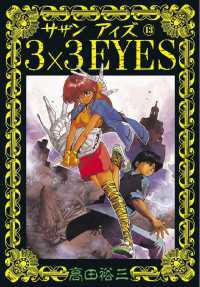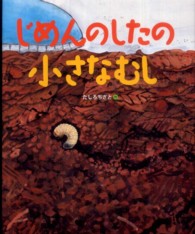内容説明
長年にわたってトチ林を取材してきた著者が、四季を追いながらトチの木と人との関わりを写真と文で語ります。
著者等紹介
太田威[オオタタケシ]
1943年、旧満州(中国東北部)生まれ。山形県大山町に引き揚げ後、郷里の山や川、海をめぐり、自然に親しむ。東北のブナ林を中心に、自然、動植物、山里の人々の生活の撮影と調査を続け、1974年写真家として独立。尾浦の自然を守る会、日本自然保護協会、日本野鳥の会、日本自然科学写真協会に所属(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kawai Hideki
73
トチの木とその周辺の生活をめぐる1年を追う写真絵本。春に出た若芽は、緑に輝く葉になり、初夏には花が咲く。すると、ハチ屋がやって来て、トチのハチミツを集めていく。秋はあふれんばかりにトチの実がなり、ネズミたち森の動物は恩恵に預かる。人間たちもトチの実を集め、手間をかけて渋抜きをしてトチ餅をつく。お正月のトチ餅をつき終える頃、トチの大木は雪に埋もれて眠る。時代を遡れば、縄文時代の遺跡からもトチの実はたくさん出ているという。茶色くてツヤツヤしたトチ餅が美味しそうだった。2016/10/02
アナクマ
37
びっくり。「川でつかまえた大きなイワナやサクラマスのハラワタをぬき、塩をまぶしてからトチの葉っぱでつつみ、ワラでぐるぐるまきます」その名は新巻。これを土に埋め、冬のタンパク源にするという。茶色に輝く杵つきのトチ餅とトチ蜜と併せて、どうしても触れてみたい食文化がここにもある。◉集団でのトチの実拾い、庭先での乾燥、また、樹下のカタクリ、それぞれは今もある風景だろうか(06年刊、12年新編)。自然の豊かさ(巨木の存在)と地域社会の充実(担い手の存在)が、文化の多様性を支えている好事例を記録した一冊です。2022/09/14
のぶのぶ
32
我が町から、北へ車で二時間近く、とちもちが名物な町がある。久しぶりにホームページを見ると、もち以外にも、トチの実を使ったものが食べられそうである。直虎のロケ地の山城があるから、ドライブにでも思ってしまった本。とちの木は、実だけではなく、葉も腐りにくくする作用があるようだ。生活に密着した木のようだ。今は、なかなか手間がかかるようだ。小さい頃、近くの神社にぎんなんを拾いに行き食べたり、よもぎを摘んだり、そういうことがまだあったが、今は、ないなあ。山の職場にいた頃、長藤の若葉のてんぷらが美味しかったこと。2018/12/26
モリー
32
夏に訪れた仙台市野草園でトチの大木に出会って以来、トチの木の事をもっと知りたいと思っていました。トチの木は、縄文時代から人々がその実を食していたそうです。葉は魚を包めばよく保存してくれるし、ミツバチに花のミツを集めてもらえば、人気のトチ蜜に、大木はくり抜けば丸木舟に、また、トチの木で作るお椀もあるそうです。もち米と混ぜて杵でよくつきあげたトチもちは、ほろ苦さが、やがて甘みにかわる美味しいおもちになるそうです。三、四日はかたくならず、カビも生えにくくて長持ち。トチ蜜にトチもち、どちらも食してみたい。2018/11/12
Maiラピ
29
『縄文人もその実を食べ、利用していたトチの木。トチの木と人との関わりを30年にもわたってトチ林を取材してきた著者が、四季を追いながら、美しい写真と文で語ります。』 トチの木って全然今まで注目してなかったけど、人はずいぶんとお世話になってる木なんですね。新巻きまで 。しかもくねくね表情豊か。近場でトチの木を検索したら、どこにでも一本は天然記念物としてトチの木の長老がいらっしゃるみたいです´ω`*是非会いに行ってみよう、もっと暖かくなったらね。2012/02/22