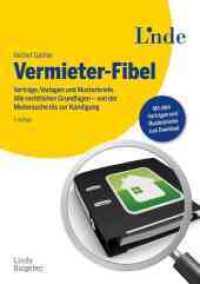出版社内容情報
鉛筆ができる過程と、それにたずさわるスリランカ、アメリカ、日本など、各国の人びとの労働と生活、考え方を記録した絵本。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
218
国語の教科書で印象的だった1冊。あらゆるものがいろんな人の手を渡って自分に届くと言うのが当時も新鮮だった。しかも谷川俊太郎氏が書いてると言うのもすごい。詩人のイメージが強いので、、、2021/09/20
南
31
使い込んで短くなった鉛筆が表紙。谷川さんが使ってきたものかな?。鉛筆って、黒鉛だけじゃなくて粘土も混ぜて焼いていたんだ。長方形の板、芯、板とサンドして六角形にカットしているんだ、など、知らないことばかりだった。2019/02/06
spatz
29
一本の鉛筆にも、こーんなにたくさんの人たちの手が通ってここにあるんだよ、と、その仕事に関わる人や家族、子供の生活の様子を交えて。発行が1985年なので今とは様子が違うところもあるかもしれないけど。スリランカ ボガラ鉱山/黒鉛を掘るアメリカ シエラネバダ/ヒノキの伐採皮を剥かれた木は一年間乾燥させたあと、板に加工。メキシコのコンテナ船にて西海岸から横浜へ。山形県、川西の、三菱鉛筆の工場。川崎市東柿生の商店。2017/04/28
おくらさん
21
自分が知ってることなんて、ちっぽけなことなんだ。 知らないことの方が多いことに ハッとする。 人間は鉛筆いっぽんすら自分1人では作り出せない。 いまではどこのうちの引き出しにも転がっている鉛筆だが、その一本の鉛筆をつくりためには、数えきれぬほど大勢の人がチカラをぁせている。 2021/02/03
絵本専門士 おはなし会 芽ぶっく
19
『いっぽんの鉛筆のむこうに』 たくさんのふしぎ|(1985年4月号) 谷川 俊太郎 文/坂井 信彦 写真/堀内 誠一 絵 1本の鉛筆の向こうには、世界の友だちの生活があるのですね。1本の鉛筆が作られて売られるまで人と人との繋がりを通して谷川俊太郎さんに言葉で伝えられます。 5月2日は『鉛筆の日』2018/10/03