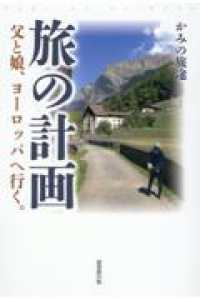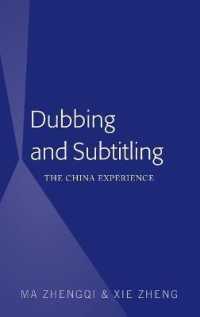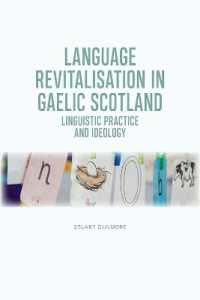出版社内容情報
時代の要請とやらで大学も実学重視の風潮。そんななかでますます旗色悪い文学部だが、人文学の疲弊は国の潜在力の低下を招くのではないか。事を有用無用の次元で考えても、現代の喫緊の課題を考えるためには、まずは人間の幅、多様な価値観を身につけることこそが必要なのだ。混迷を深める現代社会にとって、まさに、いまこそ文学部の出番である。文学部の文明史的な意義をも考察したブックレット。
プロローグ……文学部が消える? 塩村 耕(名古屋大学文学研究科教授)
1 人文学の活性化のために考えておくべきこと 日本の文学部より
目次
プロローグ 文学部が消える?
1 人文学の活性化のために考えておくべきこと―日本の文学部より
2 サンスクリット古典学からの提案―インドの文学部より
3 「廃墟」としての人文学―ヨーロッパの文学部より
エピローグ ただ引き返したらんは余りに云ふに甲斐なく覚え候
著者等紹介
塩村耕[シオムラコウ]
名古屋大学文学研究科教授(日本文学)。1957年、神戸市生れ。東京大学文学部国文学専修課程卒業。専門は、井原西鶴の浮世草子を中心とした近世前期文学、書物文化史、雨森芳洲の伝記など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
yuki
15
編者である塩村教授はかつての恩師なので、「久しぶりの塩村節だわ~」とニヤニヤが止まらなかった(笑)。 私は高校時代からゴリゴリの理系で、大学の途中で文転するという(しかもゴリゴリの文学部)、周りから見ると意味不明な経歴を持っており、毎回「なぜ?」「もったいない」と批判される。確かに、文学部で学んだ事は実用的なものではないから、第三者からは認められづらいけれど。文学部の先生方は皆、授業の途中で「本当に面白いね!」と顔を輝かせていたことを、このブックレットを読んで思い出した。それこそ学問の本髄なのでは無いか。2020/05/04
樂
3
おもしろいテーマ。タイトルの良さもあってそこそこ話題にもなった(ぽい) 個人的には和田先生のインド留学記がおもしろい。 実学至上主義に対し文学部がどこまで戦えるか。 僕はこういうヤンチャで無鉄砲な文学部の方たちがわりと好きです。2017/12/28
mittsko
3
名古屋大学文学部が2014年3月に開催したシンポジウムの記録 日本古代文学、インド哲学、西洋美術史の教授が 文学部解体の趨勢のなか「人文学の逆襲」を語りあげる 文学部の意義をめぐる文学部(人文学部)内部からの議論として 論点は大方出揃ってる 力づよく頼もしく思われる半面、残念さの印象ももった 思索と歴史と文化と言語は人間にとって本質的である―このこと自体を全否定する人は実はあまりいないはず なのに、文学部解体が叫ばれる… この歴史的な力学により自覚的なのは 巻末の来場者コメントの方じゃないかな、と2015/05/21
まのん
2
先生方には悪いけど、巻末コメントの方が興味深く読めた。その一つに「プレゼン力は最近の意識高い学生の方がある」なんてのもあったりね。2016/02/12
ドミニク
2
★★★★☆ 名古屋大学で開催された同名のシンポジウムにおける講演の記録。題名は勇ましいが、必ずしも効果的なカウンターにはなってはいない。しかしそもそも文学(部)は戦いには慣れていない(佐々木中のようなタイプは除く)のであり、本書のように、文学(部/研究)の意義を諄諄々と説くもので良いと思う。それで心ある人には届くのではないか(もちろん、多田一臣東京大学名誉教授のような、痛快な発言も楽しい)。哲学・文学・史学に関わる人、それらを好む人には是非とも手に取って欲しい一冊。2015/04/12