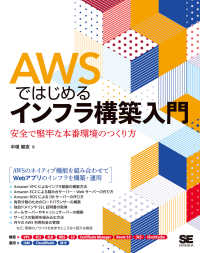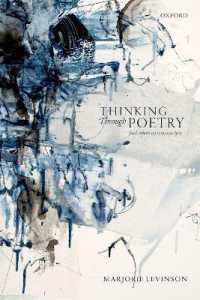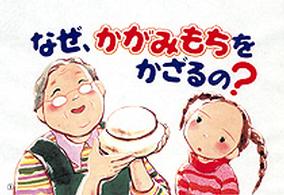内容説明
社会構成史と思想史の両面から、中世社会の構造を解き明かす。日本中世史研究における不朽の名著待望の再刊。
目次
顕密体制論の立場―中世思想史研究の一視点
王法と仏法
愚管抄における政治と歴史認識
日本宗教史上の「神道」
「院政期」の表象
軍記物語と武士団
太平記の人間形象
楠木正成の死
歴史への悪党の登場
変革期の意識と思想
中世における武勇と安穏
「中世」の意味―社会構成史的考察を中心に
思想史の方法―研究史からなにを学ぶか
著者等紹介
黒田俊雄[クロダトシオ]
1926年富山県に生まれる。1948年京都大学文学部史学科卒業。1960年神戸大学教育学部助教授を経て、1961年大阪大学文学部助教授、1975年同教授。1989年同大学を停年退官、大谷大学文学部教授。1993年没
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
12
著者の史観を伝える小論を集成した一冊。とりわけ「日本宗教史上の「神道」」が印象に残った。仏教や儒教など外来の思想に対し、神道は日本人の心性を奥底で規定する存在と捉えられることが多いが、本当にそうなのか?という大胆な疑問。本地垂迹説が織りなす壮大な思想体系の中、「神道」は仏教的世界観の一部を構成するものにすぎなかったのでは、と。著者は仏教の影響を大きく見すぎているきらいはあるが、それを差し引いても検討に値する問題と思う。2024/11/15
moonanddai
7
再読でどれだけ理解が進んだかは、ちょっと疑問…。面白かったのは「神道」について。どうやら、「神道」という宗派は、明治になってからの神仏分離によって生まれたもので、それ以前、民族宗教としての神道、「神道的な文化意識」もなく、むしろ神仏習合、本地垂迹の理論で(顕密)仏教に包摂されるというか仏教の日本的形態だと…。現世のことは神様、来世のことは仏様というのは、こういった意識が歴史的に積み重ねられてできた「古層」だということでしょう。2022/04/13
moonanddai
7
古代の仏教を考えるため、中世仏教界を説明する「顕密体制」について知るため手にしました。顕密体制とは、顕教・密教の八宗派が「国家権力と相互依存の関係を公認し合って精神界を支配する」ものとされ、鎌倉時代においても引き続きこれが主体でした。いわゆる鎌倉新仏教と言われるものも、宗教改革の端緒として現れるものの、扱いとしては異端、弱小ということになるようです。鎌倉は武士の時代という通説ではなく、貴族・武士・寺社の「権門」の力関係の推移の中で、この顕密体制というものを見ていかなければならないのでしょう。2020/10/27
御光堂
1
神道の問題について、「神仏分離によって神道は過去の日本人が到達した最高水準の宗教的哲理から切り離され、不可避的にかつ作為的に原始的な信仰そのもののような相貌を呈するようになった。神道は宗教でないと強弁されるような宗教に転落した」と指摘。
南註亭
0
1983年刊行の元版を1984年3月に読んだ。 品切れ状態が続いていたが増補新版が出版されている。