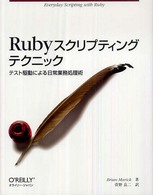出版社内容情報
「家」制度の視点から、真宗諸教団の社会構造を解明した宗教社会学における記念碑的名著が、装いを新たに約50年ぶりに復刊!東西本願寺を中心とした真宗系譜教団の構造に、社会学における「家」制度研究の視点から迫り、「家」制度を構成原理とする真宗教団の近世的構造を明らかにする。さらに近代以降の構造にも目を配り、教団の構成が「家」制度の原理から次第に離れ、太平洋戦争後、親鸞の同朋教団という理念が新たに宣伝されていく過程を描く。
近世から近代における長いスパンにおける教団の制度的展開を文献研究と実地調査にもとづく実証的な手法で読み解いた、宗教社会学における記念碑的名著が、50年ぶりに待望の復刊!
**************
まず、教団の基礎的構成単位を個々の寺院に求める。しかして住職の世襲制に注目して寺院をば住職家を中核とする檀家(門徒)群の家連合と把握し、かような寺院からなる教団を本山住職家を棟梁とする譜代の主従的家連合をみる。いいかえると、寺院については寺檀関係、教団については本末関係という構造軸を、とくに家関係として分析するのがわれわれの方針である。この方針は教団の近世的形態に即するものであるが、近代以降の体質変化は、近世の教団像をいわば理念型とする時それからの距離として測定することができる。それゆえ、この方針によって単に真宗教団の社会的存在形態が論理的にまた歴史的に解明されうるばかりでなく、併せて日本人の宗教意識の一面があらわにされ、さらに、「家」制度の究明にも一つの貢献をなすことができるであろう。(「要約」より)
**************
※本書は1978年に創文社より刊行された『増補版 真宗教団と「家」制度』を底本に復刊したものです。
序
第一章 研究方針
第一節 仏教教団の研究
第二節 真宗教団研究の方針
第二章 寺院分布
第一節 寺院の語義
(一)寺院の一般的語義
(二)真宗における「寺院」
第二節 寺院の成立
第三節 寺院の分布
第三章 真宗門徒
第一節 真宗門徒の社会的性格
(一)真宗門徒の生活態度
(二)習俗の真宗化
第二節 真宗門徒の教団内婚
(一)奥能登、町野町川西の概況
(二)川西における教団内婚
第三節 地域門徒団
(一)奥能登、町野町川西の事例
(二)愛知県渥美郡波瀬の事例
(三)広域門徒団
第四章 寺檀関係
第一節 寺檀関係の設定とその内容
(一)檀家制度の成立
(二)寺檀関係の設定
(三)寺檀関係の内容
第二節 寺門徒団
第三節 村落における住職家
(一)一部落一ヵ寺の場合
(二)飛?の毛坊主
第四節 重層的寺檀関係
(一)二種の重層的寺檀関係
(二)二段の重層的寺檀関係
第五章 末寺関係
第一節 組
第二節 組寺関係の諸類型
(一)報恩講の互助
(二)葬儀の導師関係
(三)組内の派閥関係
第三節 近世の本坊寺中関係
(一)寺中の成立と分布
(二)酒田浄福寺の事例
(三)須坂勝善寺の事例
(四)薩摩善照寺の事例
(五)井波瑞泉寺の事例
第四節 近世の上寺下寺関係
第五節 宗門法上の従属寺院
(一)『宗規綱領』における従属寺院
(二)『宗規綱領』に対する反応
(三)大谷派の附属寺
(四)附属寺制度を支えたもの
第六節 従属寺院の独立
(一)明治・大正期の事例
(二)太平洋戦争後の動態
第六章 大坊をめぐる合力組織
第一節 本流院の寺院構成
第二節 年中行事と合力組織
第三節 特別法要と合力組織
第四節 葬儀における合力組織
第五節 寺中と下道場
第七章 本末関係
第一節 末寺役と本山の権威
第二節 中世末の本願寺における一家衆
(一)本願寺一家衆の構成
(二)一家衆が果した役割
(三)宗教的権威の問題
第三節 近世真宗本山の猶子関係
(一)ヤシナイゴの三種
(二)摂家と真宗本山
(三)門跡の猶子
(四)五箇寺の猶子関係
(五)猶子関係の変質
第四節 近世の本末関係
(一)本末制度の確立
(二)本末関係と寺格
(三)本末関係の性格
第五節 明治初年の本山改革
(一)本山の構成―専修寺を中心として―
(二)本山の改革
(三)本山と法主家の分離
第六節 本末関係の変化
(一)明治以降の本末関係の変化
(二)戦後の本末関係の変化
第八章 真宗教団と「家」制度
第一節 真宗寺院の相続制度
(一)嫡系相続
(二)家督相続と住職襲職
(三)戦後の動向
第二節 真宗教団と「家」制度
(一)真宗教義と「家」制度
(二)米国仏教会と「家」制度
要 約
補 註
追 補
あとがき
新版あとがき
索 引
森岡清美[モリオカ キヨミ]
著・文・その他
目次
第1章 研究方針
第2章 寺院分布
第3章 真宗門徒
第4章 寺檀関係
第5章 末寺関係
第6章 大坊をめぐる合力組織
第7章 本末関係
第8章 真宗教団と「家」制度
著者等紹介
森岡清美[モリオカキヨミ]
1923年10月三重県に生まれる。三重県師範学校、東京高等師範学校、東京文理科大学哲学科卒業。東京教育大学文学部助教授・教授、同大学廃学時の文学部長、成城大学文芸学部教授、学部長、同大学民俗学研究所所長、淑徳大学大学院特任教授を歴任。学界では、日本社会学会会長、日本家族社会学会会長、日本学術会議会員(15期・16期)を務め、現在、東京教育大学名誉教授、成城大学名誉教授、大乗淑徳学園学術顧問。文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 漫画ゴラク 2023年 11/10 号…
-

- 洋書
- LE CHOIX