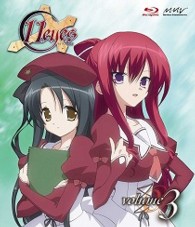出版社内容情報
地蔵盆に秘められた京都の「記憶」
祇園祭などと並ぶ夏の風物詩が語る歴史――
夏休み終盤、京都市内で子どもたちの無病息災を祈って町ごとに催される「地蔵盆」。祇園祭や五山の送り火と並ぶ「夏の風物詩」とされながら、その来歴を知る人は京都でも少ない。
本書では、子どもたちの流行現象に起源をもつ地蔵盆が、禁止令や疫病などを乗り越え、形を変えて現代へと至る過程を丹念にたどり、都市京都に根づいた歴史的意味を文献と実地調査を通して考える。
京都の都市文化をより深く知るための鍵となる一冊が、近年の地蔵盆事情などを記した補章を加え、装い新たに再登場!
■地蔵盆とは?■
毎年地蔵菩薩の縁日である8月24日頃に京都の各地で実施される年中行事。「お地蔵さんが子どもを守る」という理解から、「子どもたちの祭り」と一般的には認識されている。京都のみならず、近郊の大阪・兵庫・滋賀などでも一部実施されているが、京都で特に盛んに行われていることから、京都の盆行事の特色とされ、京都の都市文化を知るうえで欠かせないものと言えるが、これまでその歴史研究は皆無であり、本書は京都の地蔵盆の歴史研究に初めて本格的に取り組んだ1冊といえる。
■目 次■
序 章 地蔵盆の風景
第一章 京都のお地蔵さま
第二章 地蔵祭のはじまりと京都
第三章 近世都市京都と地蔵祭
第四章 近代の地蔵祭
第五章 地蔵盆の近現代
終 章 地蔵祭から地蔵盆へ
補章1 近代初頭大阪における「地蔵」
補章2 二〇一七~二四年 京都地蔵盆の「歴史」管見
地蔵盆関係略年表 ほか
【目次】
序 章 地蔵盆の風景
第一章京都のお地蔵さま
一 地蔵菩薩の伝来と広がり
二 中世の地蔵信仰
三 泰平の時代と地蔵菩薩
四 六地蔵めぐり
第二章 地蔵祭のはじまりと京都
一 中世の墓と石仏
二 「地蔵祭」のはじまり
三 発見される石仏
四 弘法大師の地蔵尊
五 一七世紀の京都
六 「地蔵会」か「地蔵祭」か
第三章 近世都市京都と地蔵祭
一 京の町と地蔵祭
二 領主が始めた地蔵祭
三 宗教者と地蔵信仰
四 木戸と町
五 運営と行事
六 もうひとつの〝地蔵盆〟――大日会
七 停止・中断させられる地蔵祭
第四章 近代の地蔵祭
一 「お地蔵さま」が消えた日――明治四~五年の廃止
二 お地蔵さまの撤去と地蔵祭の中断
三 明治一六年のできごと
四 明治一六年の布達
五 マス・メディアと地蔵盆
第五章 地蔵盆の近現代
一 明治期の歩み
二 大正期の地蔵盆
三 戦時体制下~戦後社会と地蔵盆
四 現在の地蔵盆
終 章 地蔵祭から地蔵盆へ
一 地蔵祭・地蔵盆の四〇〇年
二 近世と近代の間
三 地蔵祭・地蔵盆の祭祀
四 かつての町居住者への供養
五 地蔵盆がつなぐもの
補章1 近代初頭大阪における「地蔵」
はじめに
一 地蔵と往来
二 地蔵と道祖神
おわりに
補章2 二〇一七~二四年 京都地蔵盆の「歴史」管見
はじめに
一 地蔵盆の戦後史
二 地蔵盆と現代
三 新型コロナウィルスと地蔵盆
地蔵盆関係略年表
【参考文献】【引用史料】
あとがき/文庫版あとがき
内容説明
夏休み終盤、京都市内で子どもたちの無病息災を祈って町ごとに催される「地蔵盆」。祇園祭や五山の送り火と並ぶ「夏の風物詩」とされながら、その来歴を知る人は少ない。本書では、子どもたちの流行現象に起源をもつ地蔵盆が、禁止令や疫病などを乗り越え、形を変えて現代へと至る過程を丹念にたどり、都市京都に根づいた歴史的意味を文献と実地調査を通して考える。京都の都市文化をより深く知るための鍵となる一冊が、近年の地蔵盆事情などを記した補章を加え、装い新たに再登場!
目次
序章 地蔵盆の風景
第一章 京都のお地蔵さま
第二章 地蔵祭のはじまりと京都
第三章 近世都市京都と地蔵祭
第四章 近代の地蔵祭
第五章 地蔵盆の近現代史
終章 地蔵祭から地蔵盆へ
補章1 近代初頭大阪における「地蔵」
補章2 二〇一七~二四年 京都地蔵盆の「歴史」管見
著者等紹介
村上紀夫[ムラカミノリオ]
1970年愛媛県生まれ。大谷大学大学院文学研究科博士後期課程中退。博士(文学)(奈良大学)。奈良大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
kenitirokikuti
田中峰和
-

- 洋書電子書籍
- DIFFUSION MRI OF TH…