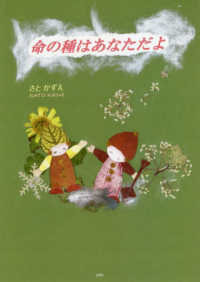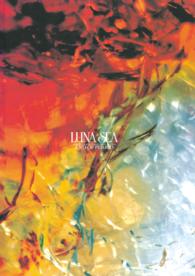出版社内容情報
日本の農業人口はこの10年で2/3まで減少し、その半数が70歳以上です。でも耕す人が減り田畑が余っている状況は、農業をはじめたい人にとってチャンスでもあるのです。今、全国の自治体が移住や就農を支援する体制を整えています。さまざまなスタイルで働く8組の農業者の姿を紹介、農業の歴史や基本技術から就農の実際までを解説します。
目次
カラー口絵 農業の現場を見てみよう
第1章 ドキュメント 「農」に生きる!
1. 観光農園に就職して果樹栽培
酒井 真梨 さん(有限会社 平田観光農園)
2. 農地を守り稲作、花き(切り花)の栽培
笠原 尚美 さん(新潟県阿賀野市農業委員)
3. 酪農とチーズ・ジェラートの加工販売
馬上 温香 さん(株式会社 牛かうVaca)
4. 先端技術でトマトの養液栽培
山本 聡 さん(株式会社 Hundred Smile)
第2章 農業者の世界
■ 日本の農業の姿
■ 農業の基本的な技術
■ さまざまな農業
■ 流通の仕組み
■ 世界の中の日本の農業
ミニドキュメント
1. 洋ラン栽培と地域の鳥獣害対策
宮川 将人 さん(有限会社 宮川洋蘭)
2. 新規参入して野菜の露地栽培
田島 友里子 さん(こばと農園)
3. 移住して稲作と農家レストラン経営
高谷 裕治 さん、絵里香 さん(農業生産法人合同会社蒜山耕藝)
4. 土づくりに挑み野菜の露地栽培
松葉 和弘 さん
■ 収入と生活
■ 農業という仕事のこれから
3章 なるにはコース
〇 適性と心構え
〇 就農の実際
【Column】 都市で営み・楽しむ、さまざまな農業
ミニドキュメント
5. 農業系高等学校で学ぶ
東京都立農芸高等学校
【Column】 農業と福祉が手をつなぐ「農福連携」
◇ なるにはフローチャート
◇ なるにはブックガイド
◇ 職業MAP!
著者略歴
著・文・その他:大浦 佳代
ライター・フォトグラファー。海と漁の体験研究所主宰。東京海洋大学修士課程修了。農村や漁村の生活・文化・都市との交流などをテーマに取材・執筆している。著書に『牧場・農場で働く人たち』『港で働く人たち』『漁師になるには』(ぺりかん社)、『つくって楽しむ わら工芸1・2』(農山漁村文化協会)、共著に『森の学校・海の学校』(三晃書房)などがある。
内容説明
自然の中に身を置き、社会状況にも向き合いながら自分らしいスタイルで生き生きと働く農業者を紹介。農業の未来、基本技術、仕事の実際から“なり方”まで解説!
目次
1章 ドキュメント「農」に生きる!(観光農園に就職して果樹栽培(酒井真梨さん・有限会社平田観光農園)
農地を守り稲作、花き(切り花)の栽培(笠原尚美さん・新潟県阿賀野市農業委員)
酪農とチーズ・ジェラートの加工販売(馬上温香さん・株式会社牛かうVaca) ほか)
2章 農業者の世界(日本の農業の姿;農業の基本的な技術;さまざまな農業 ほか)
3章 なるにはコース(適性と心構え;就農の実際)
著者等紹介
大浦佳代[オオウラカヨ]
ライター・フォトグラファー。海と漁の体験研究所主宰。東京海洋大学修士課程修了。農村や漁村の生活・文化・都市との交流などをテーマに取材・執筆している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
momogaga
あこ
黒とかげ
cesk#cesk