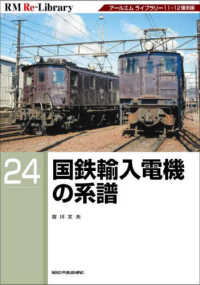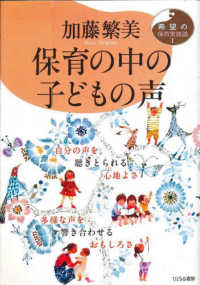- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 日本の哲学・思想(近代)
内容説明
「帝国」日本という機構、近代思想と西洋の出会いとしての明治思想、近代を規定するキリスト教と仏教の系譜、大正教養主義とアナーキズムの可能性、京都学派の課題と皇国史観の多様性、戦中と戦後の連続性―従来の近代思想史の枠組をのりこえる新しい見方。
目次
総論 近代の思想
「演説」と「翻訳」―「翻訳合議の社」としての明六社構想
福澤諭吉と明治国家
近代日本における「基督教」
明治国家と宗教
人格主義と教養主義
荒れ野の六十年―植民地統治の思想とアイデンティティ再定義の様相
明治ソーシャリズム・大正アナーキズム・昭和マルクシズム―近代日本の哲学と京都学派
日本主義と皇国史観
戦時中の戦後思想―「メディア」と「文化」の連続性から
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
14
全章、とても面白く読んだ。特に與那覇潤が植民地帝国日本を書いた「荒れ野の六十年」が面白い。天皇という普遍性を欠如したイデオロギーを、植民地に定着させることが出来なかった日本。後の「日本主義と皇国史観」でも触れられているが、天皇を主軸に据えたところが、日本のナショナリズムの弱点となったのだろう。近世、現代との時間的連続性、アジア諸国との空間的連続性を意識した研究が必要であると感じた。2020/03/07
bapaksejahtera
4
ソ連とマルクス主義の崩壊前後に注目して近代思想史の変遷を見ると思わず笑いたくなる状況がある。ペリカン社のこのシリーズは比較的最近の状況を映すシリーズとしては適当と見て最近読んでいる。本書は総論から始まって「演説」と「翻訳」以下「戦時中の戦後思想」までの各章と若干のコラムからなる。かなりわかりやすい文章で書かれている。この中では冒頭章や「福澤諭吉と明治国家」や「明治国家と宗教」が面白いが、天皇信仰さえ「愚民籠絡の道具」であり日本主義にも「天皇は『器』であり機関」とする思想の流れが語られる所は印象的であった。2020/03/02
Hiroki Nishizumi
2
與那覇潤の荒れ野の六十年を目当てに読んだ。学術書だけあって読みにくいところも多々あったが、参考になった。2022/01/08
ぽん教授(非実在系)
2
総括的、と編者は書いているが実際は各執筆者たちの論文の寄せ集め感しかしない。とはいえ各論考はそれぞれ面白くためになるので、疑問点や批判した方が良さそうなところも含めて参考になる。京都学派のものと日本主義のものは整理用としての価値があると感じたので個人的にすごく有用。2019/08/08
陽香
2
201306302017/07/16
-
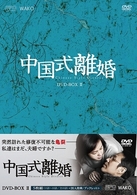
- DVD
- 中国式離婚 DVD-BOX Ⅱ