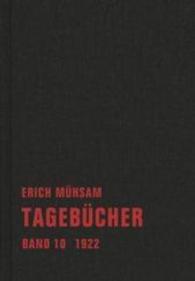出版社内容情報
《内容》 臨床心臓病学を学ぶ医師にとって,心臓核医学をどのような状況で活用すべきかに焦点をあてて解説.他の診断手法と対比させて,その適応と限界を明らかにした. 《目次》 総論 1.総説 1.核医学検査の特徴 2.核医学検査で何がわかるか 1.急性心筋梗塞において何がわかるか ●側幅血行路と心筋血流 2.慢性期虚血性心疾患において何がわかるか ●冠血流予備能と種々の薬剤負荷法 ●心筋の微小循環障害 ●stunned myocardium と hibernating myocardium 3.心不全において何がわかるか 4.心筋疾患において何がわかるか ●心サルコイドーシスの核医学診断 ●アドリアマイシン心筋障害の評価 5.小児心疾患では何がわかるか 6.胸痛の原因として肺塞栓症は考えられないか 7.治療効果判定はどの程度可能か ●心臓外科の立場からみた心臓核医学検査 3.他の画像診断法との対比 1.超音波断層法との対比 ●核医学と心筋コントラストエコー法との対比 2.CT、MRIとの対比 3.冠動脈造影法との対比 ◆核医学検査はいかに冠動脈造影検査を省略できるか 4.核医学検査に必要な基礎知識 1.放射性医薬品にはどのようなものがあるか 2.どのような装置でとるか 3.どのように投与するか 4.どのように撮影するか ●dual isotope法の利点と欠点 5.どのように所見を拾うか ●検査による ●表示法の改良 ●定量化により得られる情報、失う情報 ●負荷検査の合併症とその対策 各論 1.タリウム心筋血流イメージング 1.虚血性心疾患の診断 2.心筋viabilityの評価 ◆ドブタミンエコーかタリウム心筋シンチグラフィ再静注法か ●予後評価にどの程度役立つか ◆逆再分布は何を示すか 3.心筋患者の評価 2.99mTc標識化合物による心筋血流イメージング 1.99mTc標識化合物の利点 2.心機能と心筋血流の同時評価 3.再灌流療法の評価 ●99mTc標識化合物とタリウムとの使い分け 3.心RIアンギオグラフィ 1.ファーストパス法 2.平衡時マルチゲート法 3.VESTによる心機能 ◆心RIアンギオグラフィは心エコーにとってかわれるか 4.障害心筋イメージング 1.99mTcピロリン酸イメージング 2.111In抗ミオシン抗体イメージング 5.123IMIBGによる交感神経機能イメージング 1.123IMIBGとは 2.冠動脈疾患への応用 3.心不全への応用 ◆糖尿病の自律神経障害がわかるか ◆不整脈の焦点がわかるか 6.123IBMIPPによる脂肪酸代謝イメージング 1.123IBMIPPとは ◆どのような収集法が最適か 2.冠動脈疾患への応用 3.心筋症への応用 7.ポジトロン断層法 1.ポジトロンCTとは 2.心筋血流評価 3.ブドウ糖代謝の検討 ●ブドウ糖代謝検査の至適条件 4.脂肪酸、酸素代謝イメージング 8.これからの核医学検査 1.血栓イメージング 2.低酸素イメージング 9.核医学検査の課題と将来展望 索引
目次
総論(総説;核医学検査で何がわかるか;他の画像診断法との対比;核医学検査に必要な基礎知識)
各論(タリウム心筋血流イメージング;99mTc標識化合物による心筋血流イメージング;心RIアンギオグラフィ;障害心筋イメージング ほか)