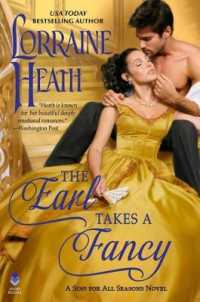出版社内容情報
《内容》 ● 高齢化の著しく進んだ現代日本の老年医学は世界のトップレベルにあるが,まだ大学に老年医学講座のなかった時代に教育を受けた多くの医師にとっては,老年医学についての認識が必ずしも十分ではない.
● 本書は,そのような医師に向けて,臨床と結びつけながら,教科書的でなく肩の凝らない読み物として,現代日本の老年医学の学問的到達点を示そうとするもの.
● 各項目冒頭には「理解のためのエッセンス」を置き,随所に挿入した「memo」欄で,より深い知識が得られるよう工夫してある.
● 簡潔な記述と多数の図表を駆使して,老年病の病態生理(メカニズム)をたいへんわかりやすく解説しており,医学生や研修医,さらにはコメディカルスタッフにもお薦めの書.
2色刷,カラー口絵18点.
《目次》
§1 何歳からお年寄り?―老化,寿命の概念と高齢期の区分―
§2 老年病とは―生理的老化と病的老化,老年症候群の考え方―
§3 高齢者総合機能評価(CGA)をどのように行うか
§4 ねたきりはなぜ起こる
§5 摂食と嚥下のメカニズム―誤嚥性肺炎をどう予防するか―
§6 食べられない高齢者の栄養管理をどうするか―誤嚥性肺炎との関連で―
§7 高齢者の意識障害の原因と対策
§8 高齢者の脱水の原因と対策
§9 めまいの原因ア・ラ・カルト
§10 高齢者の発熱をみたら
§11 貧血が進んできたら
§12 高齢者の喘鳴を聴いたら
§13 高齢者の心雑音―高齢者の弁膜症の原因と管理―
§14 胸痛がないのに狭心症?―高齢者における虚血性心疾患の特徴―
§15 高齢者の浮腫をみたら
§16 高齢者の便秘と腹痛
§17 もの忘れは痴呆に移行するか―加齢に伴う健忘と痴呆―
§18 うつと不眠にどう対処するか
§19 夜騒いで困る―夜間せん妄の病態と対策―
§20 徘徊の心理と事故の防止法
§21 腰痛,関節痛は高齢者で最も多い訴え―腰痛,関節痛の鑑別,病態生理と対策―
§22 高齢者の骨・関節X線のみかた―骨粗鬆症,悪性腫瘍の骨転移,変形性関節症,偽痛風―
§23 散歩では高齢者の筋力低下は防げない―高齢者の筋力低下のメカニズム―
§24 転倒はなぜ怖い―高齢者の歩行障害のみかた―
§25 なぜ尿が漏れるのか―頻尿と尿失禁の病態生理と対策―
§26 高齢者の高血圧管理法
§27 高齢者の白衣高血圧
§28 高齢者の糖尿病の基準は甘くてよいか
§29 インスリン療法に移行するタイミング
§30 高齢者の高脂血症の管理基準をどう考えるか
§31 診断のピットフォールとしての甲状腺機能低下症
§32 高齢者の皮膚の痒み
§33 褥瘡は一夜にしてできる
§34 コミュニケーション障害の原因と対策
§35 お年寄りの食べる楽しみをどのように援助するか
§36 高齢者の視覚障害
§37 聴力障害の原因と対策
§38 高齢者の薬剤の選択と薬用量の決め方の実際
§39 高齢女性の健康を守るホルモン補充療法
§40 高齢者の癌は本当に進行が遅いのか
§41 手術が決まったら
目次
何歳からお年寄り?―老化、寿命の概念と高齢期の区分
老年病とは―生理的老化と病的老化、老年症候群の考え方
高齢者総合機能評価(CGA)をどのように行うか
ねたきりはなぜ起こる
摂食と嚥下のメカニズム―誤嚥性肺炎をどう予防するか
食べられない高齢者の栄養管理をどうするか―誤嚥性肺炎との関連で
高齢者の意識障害の原因と対策
高齢者の脱水の原因と対策
めまいの原因ア・ラ・カルト
高齢者の発熱をみたら〔ほか〕
著者等紹介
大内尉義[オオウチヤスヨシ]
東京大学大学院医学系研究科加齢医学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。