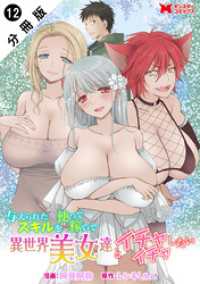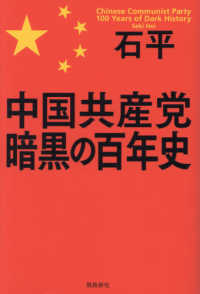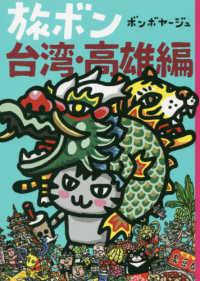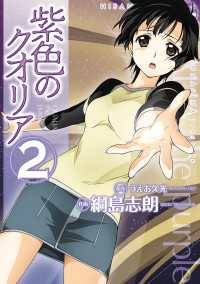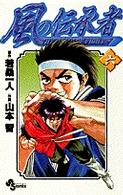内容説明
海辺で拾える一般的な貝類150種を取り上げて紹介。
目次
巻貝(ツタノハガイ科;ヨメガカサガイ科;ユキノカサガイ科;スカシガイ科 ほか)
二枚貝(フネガイ科;タマキガイ科;イガイ科;イタヤガイ科 ほか)
著者等紹介
池田等[イケダヒトシ]
1951年、神奈川県生まれ。葉山しおさい博物館館長。専門は海洋生物学、日本貝類学会会員
松沢陽士[マツザワヨウジ]
1969年生まれ、千葉県出身。東海大学海洋学部水産学科卒業。水中生物写真家として淡水魚、海水魚、水の生物を幅広く撮影。水中写真はもちろんのこと、図鑑には欠かせない標本写真も手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
62
海岸を歩いて見かける貝のほとんどはこの本で十分というのは過言ではない。図鑑に載っている貝の多くは殻が擦れていない、色が抜けていない状態のものが多い。しかし海岸に打ち上げられる貝の多くは砂や砂礫によりエージングされたものがほとんどだ。この本はそんなエージングされた状態もあわせて載っているのがありがたい。ハンディなのでかばんに入れてもかさばらず便利だ。2016/11/08
白義
10
コンセプトからして実際の磯遊び前提なのは当然なのだが、どうせ現地で拾える貝などほとんど損傷しているのだからとその損傷や摩耗状態の写真まで段階的に掲載した丁寧さは特筆すべきもの。特にタカラガイ科なんて格ゲーの2Pカラーかというばかりにクローンみたいに同じ形が並ぶので、摩耗による変化を考えたら本書のような本がないと絶対に区別などつかないだろう。ヤカドツノガイのまさにツノという感じの形など、海辺の貝といっても実際は結構形に個性の幅があるし、運がいいとオウムガイの殻まで拾えるのだとか。類書でも評判が特に高いようだ2017/07/23
kinkin
8
ハンディタイプなので海に行くときは便利な本2011/09/10
prosecco
4
石垣西表で大量にゲトした貝殻達、その同定用に入手。またコーミングしたくなること請け合いの一冊。2014/06/15
K
3
北海道以南に広く分布するツメタガイが、「ほかの貝を抱き込み、歯舌と酸で穴を開けて捕食する」とあり、その被食者の貝の頁へ行ったらまんまるな穴...これ、人為的なものと勘違いしてしまいそうだな、と思った。 写真が豊富で摩耗したものから新鮮な個体まで載せてあるのが素晴らしい。2015/04/06