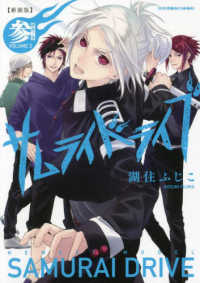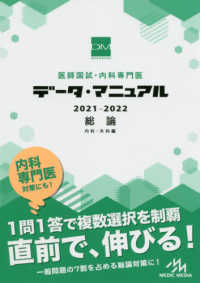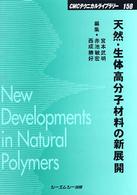内容説明
洪水のように産み出され、泡沫のように消えていく現代の出版物。点数は激増しても、その生命はかげろうの如くはかない。新刊本の「第二の人生」とも言うべき古本を扱って40年のプロが、貴重な資料をふんだんにまじえて綴る、古本業界の歴史と未来展望。
目次
開業まで
古本市場
建場廻りのことなど
古書展
蒐集―私の場合
店番
半世紀の下町業界とその未来
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
67
戦後直後からの古本屋文化が詳細に書き込まれていて資料価値も高い。それこそ古本屋さんで偶然見つけた本で買ってよかった。文学青年だった著者の鬱屈もスパイスとなっている。2019/01/16
阿部義彦
17
潰れた福武文庫です、古書市にて購入。1992年第一刷。1953年に葛飾区堀切で古本屋を営業した、著者の古本に関する回想録、自叙伝であると同時に古本の世界が垣間見え、本好きなら楽しめる内容です。自転車屋をやっていた父の仕事場の片隅に店を開くが、やがて父が死に、多数の兄弟達を養うために、色々と工夫し、やがて古本の市で振り手をするまで出世します。テレビも無い時代娯楽といえば、読書と映画くらいでした。得意分野は自筆本とそして、早くから漫画の重要性に着目します。建場から拾ったり、書店からショタレ本を買ったり逞しい。2024/06/20
Gen Kato
2
資料として。時代的流れがわかるのも貴重。2014/05/13
ヒコ。
2
戦前から昭和50年くらいにかけての古本屋店主の半生。古本の買い入れの方法(建場まわりとか、入札とか)や初版本ブーム、物価統制令による貸し本屋の隆盛、石油ショックによる古本屋の廃頽。いかにも昭和でいい2011/07/12
ラム
1
今は無き福武文庫版 反町茂雄は別格として、業界で名を成す青木の自伝 下町の古本屋が、明治古典会を通じ私淑する島崎藤村の肉筆原稿入手から変わる 著者駆け出しのころの古本業界の実態がよくわかる 一過性のものに翻弄される業界 ここがピークととっておきの良書、珍本を売り切り、気が付けば悪い品物だけが手元に 廃業した老舗古本屋談「とっておきを売りつくした時ほど惨めなものはない」 自身の蒐集についても、将来のために一分野の一定量を集め売り惜しみする勇気も説く(先輩から「君は好きで集めているだけ」とたしなめられたとか)2020/03/14
-
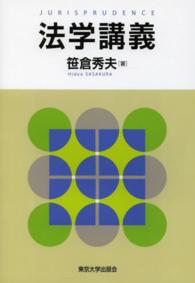
- 和書
- 法学講義