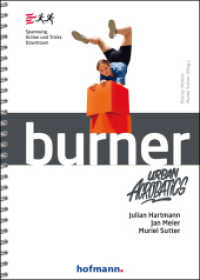- ホーム
- > 和書
- > 工学
- > 化学工業
- > プラスチック・ゴム・セラミックス
出版社内容情報
【執筆者一覧(執筆順)】
宮本 武明 京都大学 化学研究所
(現:国立松江工業高等専門学校)
岡島 邦彦 旭化成工業(株) 研究開発本部
山根 千弘 旭化成工業(株) 研究開発本部
(現:神戸女子大学)
柴田 徹 ダイセル化学工業(株) フィルター研究所
(現:ダイセル化学工業(株) 総合研究所)
吉村 美紀 兵庫県立姫路工業大学 環境人間学部
西成 勝好 大阪市立大学 生活科学部
(現:大阪市立大学大学院 生活科学研究科)
戸倉 清一 関西大学 工学部
林 良純 三晶(株) 研究所
(現:三晶(株) 中央研究所)
佐藤 貴哉 日清紡績(株) 東京研究センター
(現:日清紡績(株) 研究開発本部)
堺 修造 (株)林原生物化学研究所
(現:(財)かがわ産業支援財団 知的クラスター本部)
船見 孝博 武田薬品工業(株) フード・ビタミン研究開発本部
中尾 行宏 武田薬品工業(株) フード・ビタミン研究開発本部
吉崎 政人 三晶(株) 工業資材部
三好恵真子 大阪外語大学 開発・環境講座
大和谷和彦 大日本製薬(株) 食品化成品部
(現:大日本製薬(株)フードサイエンス部)
溝手 敦信 三晶(株)
中本 奉文 日本製紙(株) 化粧品開発研究所
中久喜輝夫 日本食品化工(株) 研究所
岡本 彰夫 電気化学工業(株) 総合研究所
則末 尚志 大阪大学大学院 理学研究所
羽室 純爾 味の素(株) 中央研究所
戸田 義郎 太陽化学(株)
藤原 和彦 日本リーバB.V.
小林 一清 名古屋大学大学院 工学研究科
鈴木 秀松 長岡技術科学大学 生物系
木村 悟隆 長岡技術科学大学 生物系
服部 俊治 (株)ニッピ バイオマトリックス研究所
高橋 真哉 新田ゼラチン(株) ゼラチン生産部
松本喜代一 元京都工芸繊維大学 繊維学部
上甲 恭平 京都女子大学 家政学部
長野 隆男 不二製油(株) 蛋白事業部
(現:愛媛大学 教育学部)
岡嶋 哲彦 不二製油(株) 蛋白事業部
(現:不二製油(株) フードサイエンス研究所)
仁木 良哉 北海道大学名誉教授
八田 一 京都女子大学 家政学部
一島 英治 創価大学 工学部
岩崎 容子 東京薬科大学 生命科学部
大島 泰郎 東京薬科大学 生命科学部
前田 瑞夫 九州大学大学院 工学研究科
(現:理化学研究所)
村田 正治 九州大学大学院 工学研究科
堀 照夫 福井大学 工学部
(現:福井大学大学院 工学研究科)
松島(二見)瑞子 桐蔭横浜大学 工学部
小寺 洋 桐蔭横浜大学 工学部
廣戸三佐雄 桐蔭横浜大学 工学部
西村 裕之 桐蔭横浜大学 工学部
稲田 祐二 桐蔭横浜大学 工学部
(現:桐蔭横浜大学 人間科学工学センター)
今中 忠行 京都大学大学院 工学研究科
熊谷 泉 東北大学大学院 工学研究科
津本 浩平 東北大学大学院 工学研究科
佐野 明彦 住友製薬(株) 生産技術研究所
(現:住友製薬(株) 製剤技術研究所)
藤岡 敬治 住友製薬(株) 生産技術研究所
(現:住友製薬(株) 製剤技術研究所)
田畑 泰彦 京都大学 生体医療工学研究センター
(現:京都大学 再生医科学研究所)
丸山 厚 東京工業大学 生命理工学部
(現:東京工業大学大学院 生命理工学研究科)
赤池 敏宏 東京工業大学 生命理工学部
(現:東京工業大学大学院 生命理工学研究科)
竹内 誠 キリンビール(株) 基礎技術研究所
黒柳 能光 北里大学 医療衛生学部
田畑 勝好 京都大学医療技術短期大学部
飯田 博樹 三栄源エフ・エフ・アイ(株) 学術部
(現:(株)マイヤー 商品制作部)
堂迫 俊一 雪印乳業(株) 技術研究所
山縣 義文 ライオン(株) ビューティケア研究所
(現:ライオン(株) 物質科学センター)
恩田 吉朗 (株)アドマテックス
(現:信越化学工業(株) 有機合成事業部)
早川 和良 信越化学工業(株) 有機合成事業部
田口 篤志 ダイセル化学工業(株) 網干工場
(現:ダイセル化学工業(株) WSPカンパニー)
(所属は1998年6月時点。( )内は2003年8月現在
【構成および内容】
総 説 宮本武明
1.はじめに
2.単純多糖と複合多糖
3.繊維状タンパク質と球状タンパク質
<材料編>
第1章 セルロース
1.セルロース 岡島邦彦,山根千弘
1.1 セルロース素材の開発方向に関する概論
1.2 特許出願からみたセルロース開発状況
1.3 セルロース構造制御による成形用原液開発
1.4 無定型構造を制御したセルロース成形体
1.5 超微粒への挑戦
1.6 セルロースの人工および化学合成
1.7 生合成セルロースの利用
1.8 他の有機原料への転換
1.9 結言
2.セルロース誘導体 柴田 徹
2.1 硝酸セルロースおよび関連誘導体
2.1.1 光学フィルム
2.1.2 繊維素材としての酢酸セルロース
2.1.3 分離膜素材としての酢酸セルロース
2.1.4 生分解性プラスチック
2.1.5 酢酸セルロースの製法革新
2.2 酢酸セルロースと関連誘導体
2.3 セルロースエーテル
2.4 光学活性物質としての利用
第2章 でん粉 吉村美紀,西成勝好
1.でん粉の用途
2.でん粉の構造
3.でん粉の糊化,老化
4.でん粉の物性改変
4.1 化工でん粉
4.2 物理的加工でん粉
4.3 多糖類混合系でん粉
4.4 その他
第3章 キチン及びキトサン 戸倉清一
1.はじめに
2.キチン及びキトサンの精製
2.1 キチンの潜在的供給量
2.2 キチンの精製
(1)化学法によるキチン・キトサンの精製
(2)生物を利用したキチンキトサンの精製
2.3 キチン及びキトサンの溶解と分子量
(1)キチンの溶解
(2)キチン及びキトサンの分子量測定
2.4 キトサンの脱アセチル化度
(1)コロイド滴定法
(2)バンスライク法
3.キチン及びキトサンの応用と新展開
3.1 医用材料としてのキチン及びキトサン
(1)キチン
(2)キトサン
3.2 化粧品材料としてのキチン及びキチン誘導体
4.その他
第4章 海藻多糖類
1.カラギーナン 林 良純
1.1 カラギーナンの原料
1.2 カラギーナンの製法
1.3 カラギーナンの構造
1.4 カラギーナンのゲル化性
1.5 カラギーナンの安全性
1.6 カラギーナンの性質
1.7 カラギーナンの用途
2.アルギン酸 佐藤貴哉
2.1 アルギン酸の構造化学的特徴とゲル化能
2.2 アルギン酸の最新利用技術
(1)創傷被覆材
(2)親水性の微粒子
(3)ナトリウム捕捉能
3.寒天 佐藤貴哉
3.1 寒天の構造化学的特徴とゲル化能
3.2 アガロースの新しい利用方法
3.3 おわりに
第5章 バイオ多糖類
1.プルラン
1.1 プルランとは
1.2 プルランの特性
1.3 プルランの利用例
1.4 プルランフィルムの特性と利用例
1.5 おわりに
2.カードラン 船見孝博,中尾行宏
2.1 カードランの性質
2.2 カードランの食品中での機能
2.2.1 品質改良剤としての利用
2.2.2 新規食品の主成分としての利用
2.3 食品向け応用検討の現状
3.キサンタンガム 吉崎政人
3.1 耐熱性キサンタンガム
3.2 シュードプラスチック性増強型キサンタンガム
3.3 まとめ
4.ジェランガム 三好恵真子
4.1 レオロジーおよび熱的性質
4.2 食品への応用
4.3 今後の展望
第6章 植物多糖類
1.ペクチン 林 良純
1.1 ペクチンの分子構造
1.2 ペクチンの性質
1.3 ゲル化剤としての利用
1.4 酸性乳ドリンク安定剤としての利用
1.5 ペクチンの用途
1.6 その他の用途
2.コンニャクグルコマンナン 吉村美紀,西成勝好
2.1 コンニャクグルコマンナンの構造と性質
2.2 コンニャクグルコマンナンの食品としての利用
2.3 その他の利用
3.キシログルカン 大和谷和彦
3.1 キシログルカンの起源と構造
3.2 食品への応用
3.3 植物中での機能
3.4 機能性食品
3.5 分子変換と物性のデザイン
3.6 将来の展望
4.グアーガム 溝手敦信
4.1 はじめに
4.2 捺染分野
4.3 ペイント
4.4 凝集剤
4.5 蓄冷剤
4.6 化粧品
4.7 おわりに
第7章 リグニン 中本奉文
1.はじめに
2.リグニンの特性
3.リグニン製品生産の現状
4.リグニン製品の用途
4.1 セメント・コンクリート混和剤としての利用
4.2 染料分散剤としての利用
5.その他
6.将来への展望
第8章 オリゴ糖 中久喜輝夫
1.はじめに
2.オリゴ糖の種類とその製造方法
2.1 オリゴ糖の種類
(1)澱粉を原料とするもの
(2)砂糖関連オリゴ糖
(3)乳糖関連オリゴ糖
(4)その他
2.2 オリゴ糖の製造方法
3.オリゴ糖の機能特性と利用
3.1 オリゴ糖の機能特性
3.2 オリゴ糖の利用
4.おわりに
第9章 トピックス
1.ヒアルロン酸 岡本彰夫
2.シゾフィラン 則末尚志
3.レンチナン 羽室淳爾
4.グアーガム酵素分解物 戸田義郎
4.1 はじめに
4.2 生理活性物質としての利用
4.3 品質改良剤としての利用
5.流動性ゲル 藤原和彦
6.糖質高分子 小林一清
6.1 はじめに
6.2 人工複合糖質高分子の分子設計
6.2.1 簡潔合成
6.2.2 水溶液中でのコンフォメーション解析
6.2.3 疎水性表面への吸着機能の発現と生物認識固体表面の設計
6.2.4 レクチンと相互作用におけるクラスター効果および高分子効果の発現
6.3 インフルエンザウイルスの感染を阻害するシアリルラクトース糖鎖高分子
6.4 今後の展開
7.エゴノリ 鈴木秀松,木村悟隆
<材料編-タンパク質->
第1章 コラーゲン 服部俊治
1.はじめに
2.コラーゲン分子の基本構造
3.構造蛋白質としてのコラーゲン
4.コラーゲンの生合成と代謝
5.コラーゲンの機能
(1)細胞の接着
(2)生理機能
6.コラーゲンの応用
(1)食品
(2)化粧品
(3)医療
7.コラーゲンの安全性
第2章 ゼラチン 高橋真哉
1.はじめに
2.ゼラチンの原料と製造
2.1 原料
2.2 製造法
3.ゼラチンの特性
3.1 物理的性質
3.2 化学的性質
3.3 化学的修飾による改質
4.ゼラチン用途の現状と展望
4.1 食品
4.2 写真
4.3 医薬品
4.4 化粧品
4.5 工業用品
5.おわりに
第3章 フィブロイン 松本喜代一
1.フィブロインの存在と組成成分
2.フィブロインの微細構造
3.フィブロインの新規溶媒と溶解性
4.フィブロインの希釈溶液と粘度特性
5.フィブロインの濃厚溶液の動的粘弾性挙動
6.フィブロインの濃厚溶液の凝固性
7.フィブロインからの再生繊維
8.フィブロインの応用展開
第4章 ケラチン 上甲恭平
1.はじめに
2.素材化技術
2.1 可溶化技術
(1)酸化法
(2)還元法
2.2 粉末化技術
3.ケラチンの特性と応用
3.1 活性ケラチンの特性
3.2 応用例
(1)ケラチンの生物学的特性と利用
(2)酸化還元特性の利用例
(3)その他の利用例
4.粉末の特性と応用
4.1 アルカリおよび酵素溶解性
4.2 吸放湿性および水分保持率
4.3 吸油性
4.4 脱臭性能
4.5 応用例
第5章 植物タンパク質 長野隆男,岡崎哲彦
1.植物性たん白とは
1.1 植物性たん白の栄養
1.2 食料資源としての植物性たん白
1.3 植物性たん白の加工特性
1.4 生理機能
2.植物性たん白の種類
3.植物性たん白の生産数量
4.植物性たん白の用途
4.1 食肉加工品としての利用
4.2 総菜への利用
4.3 水産ねり製品への利用
4.4 小麦粉製品への利用
4.5 インスタント食品
4.6 大豆たん白食品
5.植物性たん白の展望
第6章 牛乳タンパク質 仁木良哉
1.カゼイン
1.1 αS-カゼイン
(1)αS1-カゼイン
(2)αS2-カゼイン
1.2 β-カゼイン
1.3 κ-カゼイン
1.4 カゼインミセル
2.ホエータンパク質
2.1 β-ラクトグロブリン
2.2 α-ラクトアルブミン
3.牛乳タンパク質の食品素材としての機能特性
第7章 卵タンパク質 八田 一
1.はじめに
2.鶏卵およびその構成タンパク質
3.卵白タンパク質の加熱ゲル化性
4.卵白タンパク質の気泡性
5.卵黄構成成分の乳化性
6.おわりに
第8章 産業酵素 一島英治
1.はじめに
2.化学工業関連酵素
2.1 洗剤酵素
2.2 繊維素材の改質
2.3 パルプ樹脂の除去
2.4 アクリルアミドの生産
2.5 超純水の検定酵素ルシフェラーゼ
2.6 リパーゼの不斉加水分解の利用によるノック性ピレスロイドの開発
3.食品工業関連酵素
3.1 糖質関連酵素と食品工業
3.2 プロテアーゼによる甘味料製造
3.3 アミノアシラーゼによるL-アミノ酸構造
3.4 リパーゼによるカカオバター様油脂製造
3.5 ヌクレアーゼP1による5′-グアニル酸と5′-イノシン酸の製造
3.6 食品物性を変えるトランスグルタミナーゼ
3.7 プロテアーゼによるアレルゲン除去加工米の製造
4.医薬品工業関連酵素
4.1 医療用酵素
4.2 診断用酵素
4.3 医薬品素材酵素
5.増殖細胞による酵素利用
5.1 酒類工業
5.2 醤油・味噌工業
5.3 チーズ工業
第9章 分断酵素 岩崎容子,大島泰郎
1.プロテアーゼによる分断
2.タンパク質構造形成解析に用いられた分断酵素
3.遺伝子工学の応用
第10章 合成タンパク質 前田瑞夫,村田正治
1.はじめに
2.合成タンパク質の構造設計と発現
3.非天然アミノ酸を組み込んだ合成タンパク質
4.耕司構造をもつ合成タンパク質
5.おわりに
第11章 トピックス
1.セリシン 堀 照夫
2.タンパク質ハイブリッド
松島(二見)瑞子,小寺 洋,広戸三佐雄,西村裕之,稲田祐二
2.1 研究の背景とハイブリッド化による利点
2.2 PEG修飾剤
2.3 バイオテクノロジカル分野への利用
2.4 バイオメディカル分野への利用
2.5 ハイブリッドタンパク質の臨床応用
2.6 おわりに
3.タンパク質工学 今中忠行
3.1 タンパク質の構造
3.2 方法論
3.3 タンパク質の改変
3.3.1 酵素の耐熱化
3.3.2 酵素活性の増強
3.3.3 基質特異性の改変
3.3.4 酵素の最適pHの移動
3.3.5 酵素種の改変
3.4 非天然型アミノ酸のタンパク質への取り込み
4.抗体工学 熊谷 泉,津本浩平
4.1 はじめに
4.2 ファージ抗体による抗原認識能の改変
4.3 ヒト型化
4.4 抗体分子の多機能化
4.5 CDRのデザインによる抗原認識能の変換,改良
4.6 おわりに
<応用編>
第1章 医薬品
1.タンパク質医薬
1.1 DDS 佐野明彦,藤岡敬治
1.1.1 天然高分子のDDS概説
(1)糖類
(2)タンパク質
1.1.2 コラーゲンミニペレット製剤
1.1.3 おわりに
1.2 サイトカイン 田畑泰彦
1.2.1 はじめに
1.2.2 サイトカインとは
1.2.3 サイトカインの種類
1.2.4 サイトカインの医薬品への応用
2.DNA医薬 丸山 厚,赤池敏宏
2.1 はじめに
2.2 DNA医薬のカテゴリー
2.2.1 アンチセンス法
2.2.2 リポザイム法
2.2.3 3重鎖核酸法
2.2.4 デコイ法
2.2.5 変異導入法
2.2.6 アプタマー
2.3 DNA医薬をサポートする周辺技術
2.3.1 非天然型オリゴヌクレオチド
2.3.2 DNA医薬担体
3.糖質医薬 竹内 誠
3.1 糖質医薬品の背景
3.2 糖質医薬品あれこれ
3.3 ムチン・ボックスによる糖タンパク質の分子設計
3.4 GlcNAc転移酵素-?Y(Gn-T-?Y)による糖鎖分岐形成法
3.5 トランスジェニック動物による糖質医薬生産の可能性
3.6 糖鎖生合成分子育種酵母による糖質医薬生産への挑戦
第2章 生体材料
1.医用材料 黒柳能光
1.1 生体材料の人工腎臓への応用
(1)血液浄化治療
(2)セルロース系中空系型人工腎臓
(3)血液浄化用セルロース膜の生体適合性
(4)血液浄化用吸着材
(5)アフィニティ型吸着材
1.2 生体材料の人工膵臓への応用
(1)インスリン投与による糖尿病治療
(2)マイクロカプセル型人工膵臓の原理
(3)アルギン酸系マイクロカプセル
(4)アガロース系マイクロカプセル
(5)ハイブリッド型人工膵臓に使用する移植細胞
1.3 生体材料への人工皮膚への応用
(1)アルギン酸系創傷被覆材
(2)キチン系創傷被覆材
(3)コラーゲン系創傷被覆材
(4)ヒアルロン酸系創傷被覆材
(5)コラーゲンを基材とした培養皮膚
2.診断用材料 田畑勝好
2.1 臨床化学分析と診断
2.2 診断用天然高分子材料(試薬)
2.3 診断用材料(試薬)としての酵素
(1)酵素試薬の特徴
(2)酵素試薬を用いた臨床化学分析
(3)酵素の使用形態
(4)溶液状態
(5)バイオリアクターの反応素子
(6)バイオセンサーの反応素子
(7)ドライケミストリーの反応素子
(8)遺伝子検査における酵素
2.4 酵素免疫測定法(EIA:enzyme immunoassay)
第3章 食 品
1.多糖類 飯田博樹
1.1 はじめに
1.2 食品に応用される多糖類
1.3 高齢者用食品
1.4 特定保健用食品
1.5 多糖類の脂肪類似物
1.6 シンバイオテックス
1.7 おわりに
2.牛乳タンパク質の利用 堂迫俊一
2.1 はじめに
2.2 ストリングチーズ
2.3 部分加熱変性ホエータンパク質
2.4 ラクトフェリン
2.5 ラクトパーオキシダーゼ
2.6 おわりに
第4章 化粧品 山縣義文
1.化粧品とは
2.化粧品の分類
3.化粧品に使用される水溶性高分子
3.1 天然高分子
(1)植物系天然高分子
(2)動物系天然高分子
(3)微生物系
(4)多糖類誘導体
(5)タンパク誘導体
3.2 合成高分子
第5章 繊維関連 上甲恭平
1.はじめに
2.酵素
2.1 來雑物の除去
2.2 繊維の機能化と改質
2.3 その他
3.生体および天然高分子誘導体
3.1 精錬・染色・仕上げ助剤
3.2 染色性改良剤
3.3 繊維機能化剤
第6章 土木・建築 恩田吉朗,早川和良
1.はじめに
2.コンクリート用混和剤
2.1 高流動コンクリート
2.2 AE剤,AE減水剤,水中不分離性混和剤
3.安定液(泥水)
4.高分子固化剤
第7章 飼 料 田口篤志,柴田 徹
1.はじめに
2.モイストペレットの概要
2.1 粘着剤
2.2 その他の養魚飼料
2.3 その他の飼料
内容説明
本書は、天然・生体高分子の魅力とその高度利用に関して、繊維その関連、医薬品・生体材料、食品材料各分野の第一人者である宮本武明、赤池敏宏、西成勝好の3氏編集によりまとめた成書である。
目次
総説
材料編―多糖類(セルロース;でん粉 ほか)
材料編―タンパク質(コラーゲン;ゼラチン ほか)
応用編(医薬品;生体材料 ほか)
著者等紹介
宮本武明[ミヤモトタケアキ]
京都大学化学研究所を経て、現、国立松江工業高等専門学校
赤池敏宏[アカイケトシヒロ]
東京工業大学生命理工学部を経て、現、東京工業大学大学院生命理工学研究科
西成勝好[ニシナリカツヨシ]
大阪市立大学生活科学部を経て、現、大阪市立大学大学院生活科学研究科
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。