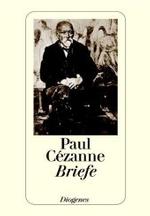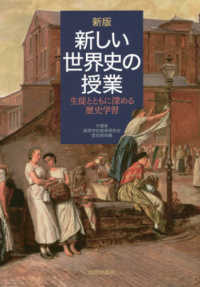内容説明
下町の少年期から「昭和天皇の死」まで。みずからの足跡をたどりながら、今や30年を隔てる「激動の昭和」を縦横無尽に斬る!!『言語にとって美とはなにか』『共同幻想論』『心的現象論』などのモチーフを自註!「三島の死」「連合赤軍事件」「反核異論」なども収録。
目次
1 戦前(少年;過去についての自註A ほか)
2 戦後(戦争の夏の日;過去についての自註B ほか)
3 主著(『言語にとって美とはなにか』あとがき;共同幻想論にゆくえ ほか)
4 昭和の終わりへ(「父の像」;母の死 ほか)
著者等紹介
吉本隆明[ヨシモトタカアキ]
1924(大正13)年、東京・月島生まれ。詩人、文芸批評家、思想家。東京工業大学工学部電気化学科卒業後、工場に勤務しながら詩作や評論活動をつづける。文学、社会、政治からテレビ、料理、ネコの世話まであらゆる事象を扱い、日本の戦後思想に大きな影響を与え、「戦後思想界の巨人」と呼ばれる。2003(平成15)年、『夏目漱石を読む』で小林秀雄賞受賞。2012(平成24)年3月16日逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
78
吉本隆明さんのアンソロジー。久し振りに吉本さんの文章に触れて感慨一入。編集は、柳田國男・高村光太郎・宮沢賢治・三島由紀夫など、吉本さんにとって重要な人物の論考を万遍なく配し、「共同幻想論」等の主著に対する「あとがき」を掲載するという正攻法。吉本さんの敗北(敗戦、労働運動の挫折、60年安保闘争)や花田・吉本論争は詳しいが、一方、「擬制の終焉」など丸山眞男先生との論争をスルーしているのは残念。私は、平成時代の吉本さん(サブ・カルチャー、オウム真理教、福島原発事故)には共感しないが、この昭和の香りは懐かしい。2021/06/01
-
![めしばな刑事タチバナ (57) [ドレッシングどれにしんぐ] TOKUMA COMICS](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2160655.jpg)
- 電子書籍
- めしばな刑事タチバナ (57) [ドレ…
-
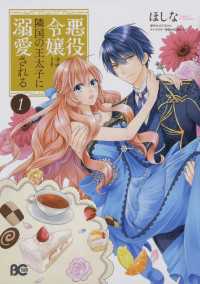
- 電子書籍
- 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される【タ…