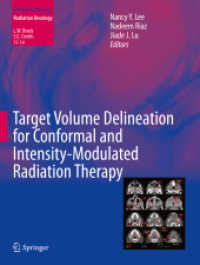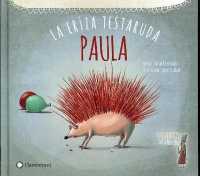内容説明
日本国憲法は、マッカーサーの押し付けであるが、それを実体化したのは宮澤俊義である。彼は、占領軍の国際法違反の憲法改正を「革命」として捉え、日本国憲法の人権規定を錦の御旗として、戦後の民主主義の理論的支柱となった。この男を研究することで、今も日本を支配するエリートたちの理論を解明することができる。宮澤が支配した東京大学法学部は、今も日本の官僚エリートを輩出する総本山だが、その頭の中も宮澤の規定した三大説の枠の中にある。
目次
はじめに―ほら、宮澤俊義は生きている!
序章 なぜ今、宮澤俊義なのか?
第1章 宮澤俊義ってこんな人
第2章 宮澤憲法学の呪い
第3章 宮澤憲法学を理解する五つの論点
おわりに―宮澤俊義は不滅なのか?
著者等紹介
倉山満[クラヤマミツル]
1973年、香川県生まれ。憲政史研究家。中央大学文学部史学科国史学専攻卒業後、同大学院博士前期課程を修了。在学中より国士舘大学日本政教研究所非常勤研究員を務め、2015年まで日本国憲法を教える。現在、ブログ「倉山満の砦」やコンテンツ配信サービス「倉山塾」やインターネット番組「チャンネルくらら」などで積極的に言論活動を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
LUNE MER
20
挑発的なタイトルであるが、本質的な対象は東大法学部ではなく、著者が認識するところの「誤った憲法解釈」を意図的に正当化した憲法学者達の功罪を糾弾する内容となっている。そもそも私が憲法の解釈に興味を抱いたのは「東大のディープな日本史」シリーズを読んでからなのだが、いま東大入試で問われている(受験生に大学側が求める)内容は本書で非難されているところのものであるのか?面白いことに、東大日本史では正にこういった論点に一石投じるかのような出題がなされているように見える。一冊の本だけを鵜呑みにすることの危険性を実感。2022/12/21
出世八五郎
17
九条、皇室典範以外にもGHQ憲法には問題があって、つか一杯あるのだろうが、運用的にも不誠実で裁判官自身が責任が持てない事案は適当に裁いている。そして、多分、機能していない。そんなGHQ憲法を後生大事にしているのが護憲派。しかし、憲法界隈では護憲派が多数派。しかも、改憲勢力は九条打破しか目に見えてない人が多数。著書の作品の中では一番難しいが概要は理解できる。宮澤俊義という東大法学部の大悪人が今の日本を呪縛している。一般人までをも呪縛している。早く改憲を!2020/07/10
軍縮地球市民shinshin
12
タイトルはこんなだが、おそらく編集者がつけたのだろう。中身は日本国憲法の「生みの親」ともいえる東大教授宮澤俊義の憲法思想である。従来宮澤は戦前・戦中・戦後と思想が変わったので「変節漢」と一部から批判があったが、著者は宮澤の思想は戦前から一貫しており、「時流迎合型」と分析する。ニヒリストであったと指摘する。現代の凡百の憲法学者とは違い、法哲学・法制史・外国憲法との比較法学をみっちり勉強し英仏独語を話せた宮澤はかなり優秀な学者である。戦前に世界一民主的と言われたワイマール憲法を、まったく改正することなく形骸化2019/06/26
積読0415
8
予想通り舌鋒鋭く、決して中立とも言えないため、敵を作る本だとは思った。しかしこの本でなくては得られない知見が在ることも、また事実だと思う。本書の大半は戦前、戦後の宮澤教授の変節(時流迎合)を詳細に糾弾していく。学会の裏話とも言えるし、一人の学者の権力闘争史と見れなくもない。政治でも、実業でもそんな話はあると思うが、如何せん、法学者の業績は後世を拘束してしまうため、昔の話として片付けるわけにもいかない。幾ばくかの法律知識は必要かと思うが、それでもこの手の本でこれ程読みやすいのは凄いと思う。 2019/12/31
読書実践家
6
戦後レジーム打破を掲げ、展開される憲法論。面白かった。2020/01/26