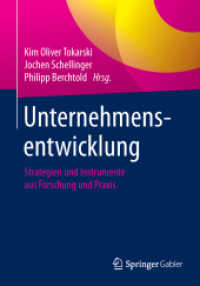内容説明
古代から中世のなかばまで、天皇に代わり、皇族の女性が伊勢神宮に仕えた。その女性を斎王(斎宮)といい、謎に包まれた部分が多い。各時代での存在意義やその生活などを明らかにし、当時の人々の信仰・宗教観を考える。また、斎宮跡周辺の散策ポイントも紹介する。
目次
第1章 古代国家と伊勢斎宮(ベールを脱ぎつつある「幻の宮」;斎宮のはじまり;斎宮と古代の政治 ほか)
第2章 王朝物語の時代のいつきのみや(伊勢物語と斎宮;伊勢神宮での斎王;百人一首と斎宮 ほか)
第3章 「古代」の終焉と斎王たち(斎宮託宣事件;斎王と女院;発掘から見る斎宮衰退の時代 ほか)
付篇 斎宮跡を歩く(近鉄斎宮駅;斎王の森;奈良時代の古道 ほか)
著者等紹介
榎村寛之[エムラヒロユキ]
1959年大阪市生まれ。大阪市立大学文学部卒業。岡山大学大学院文学研究科前期博士課程卒業。関西大学大学院文学研究科博士課程単位取得終了。現在斎宮歴史博物館主査兼学芸員。博士(文学)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
双海(ふたみ)
11
古代から中世の半ばまで、天皇に代わりに内親王などの皇族の女性が、都から伊勢の地に送られ伊勢神宮に仕えた。その女性を斎王(斎宮)といい、この制度については知られていないことが多い。斎王の各時代の中での位置づけ、生活など、その特色をわかりやすく、明かにする。2023/03/21
らむだ
4
斎王の中でも伊勢神宮に使えた皇女とその宮殿である「斎宮」に焦点をあてた一冊。斎宮の遺構・出土品や物語・日記に残された斎宮たちの姿を通じて、伊勢斎宮と斎王たちの生きた世界を辿る。巻末「斎宮跡を歩く」では現在(2003年頃?)の斎宮跡と斎宮歴史博物館の様子が伺える。2022/05/14
菜花@ほのおかくとう協会門下生
4
百人一首→平安時代→斎宮、と趣味の範囲を広げようと思ったけど、基本知識をしっかり知らない為、馴染まない箇所も多々ありました。ですので、平安時代についての章や、伊勢物語や源氏物語にみる斎宮などのページを読み、今回は満足することにします。この本を読むには、予備知識がないと難しいかもですね。再チャレンジしたいです。遷宮の前に、もう少し伊勢神宮についての知識を入れたいな、と思います。あとは、天智天皇を「天智」と表記しているのが嫌でした。2012/06/14
堆朱椿
2
斎宮入門書。わかりやすく、読みやすい。今まで斎宮はもっと巫女に近い存在だと思い込んでました。2013/11/23
ゆの字
1
突然のヅカ話に笑った。心底、宝塚が好きなのね。内容は、とても興味深く読むことが出来た。日本史と古典が好きな人にはたまらない。もっと深く斎宮について知りたいと思った。2019/10/09